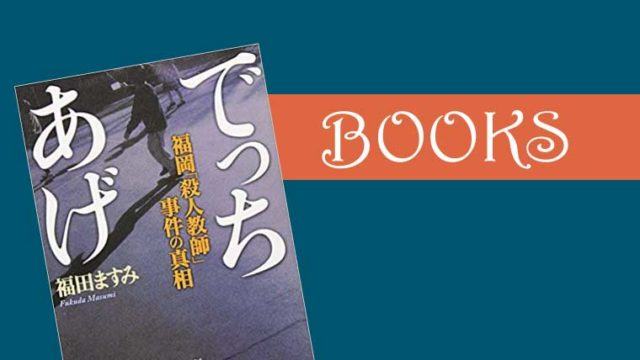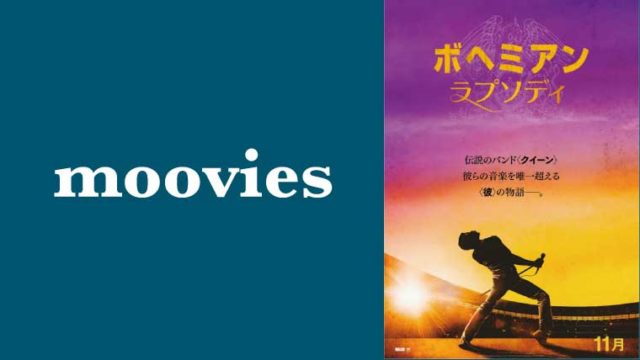今も印象が薄いことに変わりはないのだけれど、その一方で、けっこう大切なことが書いてあったという後味のようなものが残っている。それはおそらく商品経済に縛られるようにして生きている現代人の姿だろう。贈与(=非経済)というものに注目することで、今の世の息苦しさについて、一つの解釈を示してくれていると思う。
贈与
著者の松村圭一郎氏は長年エチオピアのフィールドワークを続けてきた文化人類学者。日本とエチオピアを行き来する中で感じてきた違和感を考察し、改めて今の日本を見つめ直したのがこの本だと言える。
この本は「贈与」の話から始まるんだけど、正直これまで考えたことはなかった。でもなかなか奥深いものがある。少し詳しめに整理しておく。
「交換」と「贈与」/「商品」と「贈り物」
モノのやりとりには二つの種類がある。「交換(経済)」と「贈与(非経済)」。それに応じてモノは「商品」になったり「贈り物」になったりする。「商品」と「贈り物」とでは意味合いがまったく違う。
たとえばバレンタインのチョコレートをお店で買うとき、店内に陳列されているチョコレートはすべて「商品」であり、所有権はもちろんお店にある。その中からどれかを選んで代金を支払うと、その瞬間にそれは買い主のものに変わる。代金との「交換」が成立したわけだ。これは立派な経済行為である。
しかし、そうやって買ったチョコレートを恋人にプレゼントするとき、チョコレートは別の意味を帯びる。「商品」ではなく「贈り物」。たとえホワイトデーのお返しがあるとしても、それはお店で行われた「交換」とは種類が違う。プレゼント(「贈与」)は経済行為ではない。
このように同一のモノが「商品」にも「贈り物」にもなりうる。だからややこしい。しかも曖昧は許されない。どっちでもいいや、とはならないのである。だから、取り違えを防ぐために人は細心の注意を払う。リボンを付けたり、ラッピングをしたり…。
「交換」と「贈与」の違い
で、「交換(経済)」と「贈与(非経済)」とで何が違うかというと、著者によると「思い」とか「感情」が伴うかどうか。
「交換」ではお店から購入者に商品の所有権が移るが、そこに「思い」や「感情」は必要ない。商品と引き替えに買い主が代金を支払えば、それでやりとりは完了する。店員は最高の笑顔を浮かべるかもしれないが、それは職業上の所作であって、客に対する個人的な感情を表現するものではない。
一方プレゼント(「贈与」)の場合、同じように贈る側から受け取る側にモノの所有権が移るが、代金は請求されない。返礼は期待されるものの、それはお金ではない。非経済行為にお金が介在してはいけないのだ。「贈り物」はモノにではなく、贈る側がそれに託した「思い」や「感情」にこそ意味がある。だからお金には換算できない。思いや感情を受けとめ、それに返礼しなければならない。
こんなふうに言うこともできる。「交換(経済)」には個人的な人間関係は必要ない。店員と客が親しく会話を交わすことはあっても、赤の他人のままでいい。むしろそのほうがスムースに行く。等価のモノ(この場合はモノと代金)を交換することこそが重要なのであって、それ以外のこと——人間関係とか感情とか——は邪魔なだけだ。だからできる限り排除される。経済行為は脱感情化されることで成り立っている。代金さえ支払えば人格が問われることさえもない。
「贈与(非経済)」はまったく逆だ。贈与とは思いや感情の表現そのものであり、ほとんどの場合、人間関係が前提となっている。物乞いへの施しなど例外はあるが、基本的に赤の他人にプレゼントはしない。そして、そこでは「経済」や「お金」が邪魔をする。「経済」とか「お金」の臭いがすると思いや感情が減殺されると信じ込んでいるかのようだ。だから徹底的に排除される。値札を外し、きれいにラッピングするのは、「商品」ではないことをアピールするためだ。贈り物がお金である場合でも、祝儀袋や香典袋の中に丁寧に包み込まれる。
「交換」は新参者?
当て推量だけれど、もしかしたら人類はまだ「交換」に慣れていないのかもしれない。と言うよりお金に慣れていないのか?
おそらく「交換」とは、赤の他人同士でもモノのやりとりができるように人類が編み出したものなのだろう。生きていくために、あるいはより良い生活をするために、知らない人ともお互いに必要なモノを交換する。やがて貨幣が生まれ、より多くの他人同士が交易を交わすようになる。
共同体の中では「交換(経済)」など必要なかったのではなかろうか。モノのやりとりはすべて身内同士の贈与か共有。人類の長い歴史のうちのほとんどの期間、それでなんとかしてきたのではないか。どうしても足りないモノだけ外部との「交換(経済)」で賄う。違うかな。だから、身内同士で贈り物をするときは「経済」や「お金」の臭いを消そうとする。「交換」ではないこと、つまり、あなたと私は赤の他人ではないことを証明して見せなければならないからだ。
親しい間柄に「交換(経済)」を持ち込むことが嫌われるのも、そう考えると理解できる。家族や恋人の間でモノの売買を求められたら、あまり良い気持ちはしない。それは、親しい間柄に「交換(経済)」はふさわしくないと誰もが信じているからだろう。感情の表現である「贈与(非経済)」は、愛情で結ばれた人間関係をより強いものにするが、脱感情化した「交換(経済)」は、その人間関係の否定と受け取られる。
ゲマインシャフトとゲゼルシャフト
「交換」はゲゼルシャフトを、「贈与」はゲマインシャフトを思い起こさせる。つまり、「交換」には合理的、合目的的でクールな現代的関係が、対して「贈与」には共助、共同体といった、古くから人間社会を支えてきたウェットな関係が垣間見える。
人間社会は経済の発展によってその性質を変化させてきたんだなということがよく分かるが、同時に、昔のスタイルが現代社会にしっかりと残っていることに感心する。
問題は、「贈与(非経済)」は面倒くさいということだ。贈り物に託される思いや感情は重苦しい。一方的に注がれる愛情もあるだろうが、適切な返礼を期待されることも多いし、その返礼には暗黙のルールがあったりもする。それに多くの場合、全人格的な人間関係が求められる。そういうゲマインシャフト的なものは時代とともに廃れてきているというのが実情でもある。
日本社会は「交換」が幅を利かせる社会
著者によると、エチオピア人はよく物乞いにお金を渡すそうだ。日本人を始めとする裕福な外国人は躊躇してしまうことが多いのに、貧しいエチオピア人たちはためらわずに分け与える。それを見て著者は気づく。
いかにぼくらが『交換のモード』に縛られているのかと。
いまの日本の社会では、商品交換が幅を利かせている。さまざまなモノのやりとりが、しだいに交換のモードに繰り入れられてきた。それは、面倒な贈与を回避し、自分だけの利益を確保することを可能にする。やっかいな思いや感情に振り回されることもなくなる。
しかし、この交換は、人間の大切な能力を覆い隠してしまう。
(P34)
なるほどそうだよな、と思う。お金が万能になるって、こういうことでもある。もちろん交換とかお金だけの問題ではなくて、社会全体が構造的にそういう方向へ向かっているわけだけれど、実際「交換のモード」がふつうになってしまったのは確かだろう。だから「贈与のモード」のスイッチがなかなか入れられない。
日本では、自然と感情を生じさせるような状況が社会から排除されている。(中略)それは人と人とのやりとりを「経済化=商品交換化」してきた結果でもある。
商品交換は、やりとりの関係を一回で完結/精算させる。「負い目」や「感謝」といったモノのやりとりに生じやすい思いや感情は「なかったこと」にされる。そこで対面する「人」は、脱感情化された交換相手でしかない。与えるべきものを与え、もらうものをもらったら、その関係は終わる。この交換の関係は、コミュニケーションの基礎となる「共感」を抑圧する。
(P58)
「贈与のモード」のスイッチが入れられないということは、共感を封じ込め、コミュニケーションの可能性を奪うことでもある。
しかし、我々は「交換のモード」から逃れられないわけではない。「交換の関係」もべつに絶対的なものでもなければ、固定的なものでもない。血縁を別にすれば、人と人との「関係」が最初から存在するなんてことはあるはずがなく、モノや言葉をやりとりするうちに徐々に形作られていくものだ。関係が行為を生むのではなく、小さな行為(やりとり)の積み重ねが関係を生む。そして、社会とはそういう関係の束なのだ。だから自分たちの行為、つまり他者とのモノや言葉のやりとりの仕方を変えていくことで社会を変えることができる。(P82〜84)
著者が言っているのはそういうことだ。そして、他者とのやりとりを見直すときに重要になるのが「贈与」の視点だ——なんて言うほど単純な話でもない。話題は「国家」「市場」「食料援助」へと大きく広がっていく。
「国家」「市場」「援助」
市場経済(資本主義)と計画経済(社会主義)
計画経済では、資源の配分を国家が一元的に決めていた。市場経済では、原則として、その配分の「最適値」を消費者の行動が決めていく。いわば、社会でよい(原文では傍点)とされる価値が、多数の決定者の選択にゆだねられている。(P129)
この「一元的」というやつが魔物なんだろうな。上手くいけばそれこそ究極の最適解が得られるのかもしれないけれど、それよりはラクダが針の穴を通るほうが易しい。結局のところ、志も能力もない大小の権力者があらゆることを恣意的に決めていって、不公平、不公正がまかり通る独裁国家になっていく。
僕の場合、一握りの資産家による支配から大多数の国民を解放するという、社会主義のもともとの動機には共感するのだけれど、一元化なんて至難の業だということも理解できる。
もちろん市場経済だって理屈どおりに上手くいっているわけではない。人々の自主的な決定が本当に「最適値」を生んでいるのかというと、かなり怪しいものがある。
もちろん、特定の価値選択へと個人を誘導する仕掛けがたくさん潜んでいる。沖縄在住の政治学者ダグラス・ラミスは言う。芋とかニンジンとか大豆とか豆腐とか、日々の生活に不可欠なもののコマーシャルはない。コマーシャルは、基本的にいらないものを買うように消費者を説得するためのものだ、と。この誘惑の構造が、市場を動かす力になっている。
(P130)
実はこの本で一番印象的だったのはここだった。みんな薄々気づいてはいるんだろうけれど。
それに市場では、公平とはほど遠い偏った富の配分がなされる。生まれつき多くの財産をもつ人となにももたない人が、その格差を市場のなかだけで埋めるのは至難の業だ。市場で価値あるものを手に入れるためにそれと交換する財をもたない人は、まず自分自身の身体を「労働力」として売るしかない。子どもや病人など、それができない人は、誰かに与えられないかぎり、なにも手に入れられない。市場の論理は、その不公平な配分の責任を過剰に個人に押しつける。(P130〜131)
それを是正する役割を果たすのが国家である。
市場経済と国家
市場は根本的な格差を是正できない。その偏りは、国家が徴税と社会保障による再分配で補う。また、市場が限られた企業の独占状態に陥ると、消費者は自由に選択できなくなる。商品の多様性はなくなり、市場は活力を失う。自由な競争を可能にしているのは、「ルール」であって、「放任」ではない。格差や独占を是正し、ルールの順守を監視する上位の権力として、国家が必要とされる。(P132)
そう考えると、現代の国家というのは、社会主義に近いスタンスに立って市場経済の暴走をコントロールする存在だと言えるのかもしれない。
国際援助と国家
難民や貧困国への食料援助と言えば、人類の良心を試すような大きな問題だが、案外国家のエゴで動いていたりするらしい。この本で初めて知った。
たとえばアメリカは、国内農業を保護するために農産物の価格維持政策を取っているらしい。豊作で市場価格が低迷すれば政府が買い取って価格を支える。で、これが「食料援助」に回されるのだという。どの国に送るかは外交戦略に基づいて決める。飢えた人々がいるから助けるという単純な構図ではないのだ。だから国内価格が高騰すれば援助も激減する。
要は、アメリカの政治家たちが見ているのは被援助国の貧しい人々ではなく、自国の農業関係者を始めとする有権者だという話だが、彼らだけを責めても仕方がない。援助を受ける側の国でも、政治家たちは援助物資を自分の権力強化に使おうとする。アメリカの善意など彼らにとってはどうでもいい。誰かにもらったと言うより「自分が」国民のために調達したという印象を与えたいに決まっているし、政治の駆け引きに利用できるものならためらわずに利用する。まあ、そんなもんだろうさ。(P144)
飢餓に苦しむ人々への食料援助という、国境を越えた人類愛の表現(贈与)もそれほど美しいものではないということだ。でも著者は、権力者たちのそんな思惑の絡み合いの先で、人々がしたたかに生きる姿に光を見出す。
援助国はお国の事情でダブついた物資を送りつけるわけだから、被援助国で十分に足りているモノが届くケースもあるわけだ。そんな「贈り物」は当然、市場に流れる。
経済を停滞させないために市場から引き上げられ、非経済化されて「贈り物」となった物資が、(お互い様とも言えるけれど)その気持ちを踏みにじるような形で被援助国の市場に流れ、経済化する。面白いもんだ。それだけではなくて、援助された穀物を使って酒が醸造され、宗教的な祝祭が活発化したなどということもあるそうだ。瓢箪から駒みたいな話だが、人々がそうやって新たな行動を起こして新たな関係を築き、それが束になって社会が変化していく。
著者は言う。
もうひとつ重要なのは、個人の日常的な行為のレベルが、国家や市場といった大きな動きと「連結」しながらも、かならずしも「連動」していないという点。つながってはいるが、前もって意図された方向だけに動くわけではない。そこに世界を変えるためのスキマがある。アメリカの外交戦略も、エチオピア政府の政治的意図も、いろんな人とモノの連結の過程をへて薄められていく。国家や市場の「思惑」は、最後は個人のささやかな行為のなかで解消される。(P152)
公平
国家であれ市場であれ社会であれ、どんなに大きく遠いものに見えても、不変なものはない。目の前のモノを動かすことで自分と他者との関係は変わる。人間関係が変わっていけば社会も変わる。動かし方だって、「交換」もあれば「贈与」もあるし国家による「再分配」もある。どれかが正しいのではなくて、いずれも一長一短がある。
しかし、我々はいつの間にか「交換のモード」に縛られた生活に陥っている。「交換のモード」では感情が封じ込まれ、共感が機能しなくなりがちだ。
まず、知らないうちに目を背け、いろんな理由をつけて不均衡を正当化していることに自覚的になること。そして、ぼくらのなかの「うしろめたさ」を起動しやすい状態にすること。人との格差に対してわきあがる「うしろめたさ」という自責の感情は、公平さを取り戻す動きを活性化させる。そこに、ある種の倫理性が宿る。(P174)
便利で取っつきやすい「交換のモード」。いちいち感情やら人間関係のしがらみやらに囚われないでいいから気楽なんだけれど、それって、人間らしさを放棄していることでもある。それを自覚すること。
そのとおりだと思う。