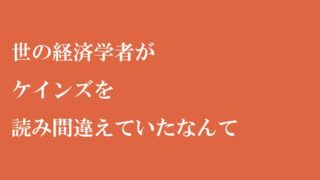2019年 日本
企画・製作:河村光庸
監督:藤井道人
出演:シム・ウンギョン、松坂桃李、田中哲司
なぜ日本では反権力的な映画が生まれないのだろうと疑問に思っていたのだが、直球ど真ん中の、とんでもない映画が誕生した。
映画情報サイトで紹介されない映画

封切り当日だというのにまったく情報が出ていなかった。「TOP」ページはもちろん、「作品を探す」ページの「上映中の映画」にも出ていない。映画名で検索してやっと見つけた。で、次のようなツイートをしてみた。
本日封切りの『新聞記者』の上映館を調べようとMovie Walkerのサイトを見たら、影も形もなかった。「TOP」ページはもちろん、「作品を探す」ページの「上映中の映画」にも出てない。映画名で検索してやっと見つけた。
映画.comは「TOP」にも「上映中の映画」にも出てたけど。
どうして? https://t.co/XIqdt0Nc3X pic.twitter.com/cfT8UFo1Dq— 亀五郎 (@kamegoro_old) June 28, 2019
すると、映画.comも前日までは渋谷と浜松しか(上映館を)載せていなかったという返信が。
まあ、いつもこうしたサイトをチェックしているわけではないから、これがどの程度異常なことなのかは分からない。しかし、それにしても映画情報サイトがその日封切りの映画の情報をシャットアウトしているというのは、やはり尋常なことではないだろう。
しかも、封切りから10日たった7月8日の時点でも状況は変わっていなかった。久しぶりに同サイトを覗いてみたのだが、やはり「TOP」ページにも「上映中の映画」ページにもこの映画は紹介されていない。目に付くところに出ているのは新着レビューが1件だけだ。検索してようやく情報に辿り着く。
ちなみに「全国週末興行成績:2019年6月29日~2019年6月30日」は10位にランクされていて、「映画の時間」というサイトには「143スクリーンという規模での公開ながら10位に初登場」というコメントがあった。前宣伝もなく上映館が極めて少ないというのに、興行的には善戦しているのだ。それなのに映画情報サイトは相変わらず情報をシャットアウトしているということだ。
要するに、反権力色の強い作品だから「政府から圧力がかかっているのでは」と言いたいわけだが、これってこの映画が描いていることそのものだったりする。政府がこの映画の公開に対して圧力をかけるとしたら、その実行部隊として動くのは、この映画が描いている内閣情報調査室のはずだからだ。ちょっと凄いことが起こっていることになる。
個人的には“弾圧という販促”だったら面白いのにな、と思わないでもない。つまり、この「弾圧」は製作側がわざと仕掛けたもので、僕のように「政府からの弾圧だ!」と疑う人間がSNSで拡散することを狙う新手の販促なのではないか、だとしたらかなりの高等戦術だなと。実際、ツイッターに投稿したわけだし。
しかし、そこまで遊べる映画製作者がいるはずもない。そして、こんなトリッキーなことを考える僕はおそらく“平和ぼけ”で、それこそ権力者の思うつぼなのだろう。たぶん凄いことが起こっているのだ。そう思ったほうがいい。
内閣情報調査室を描いたホラー映画
執拗に描かれる内閣情報調査室の不気味さにすっかりやられてしまって、新聞とか新聞記者の存在はどこか後景に退いてしまったような気がする。実際、内調の映画としか思えないというのが率直な感想だ。
もしかしたら内調にスポットを当てるというアイデアは、昨年日本で公開された韓国映画『1987、ある闘いの真実』(2017年製作)がお手本になったのかもなと思う。この映画の陰の主役は警察の対共分室(北朝鮮のスパイや思想犯を取り締まる部署)だった。民主化運動に関わる者はすべて北のスパイだとして厳しく弾圧し、逮捕者には拷問を強いた。不都合なことは隠蔽し、言論を統制する。戦前・戦中の日本で恐れられた特高警察のようなものだろうが、手にしていた権力はそれ以上だったかもしれない。その対共分室の実態を細かく描くことで、この映画は当時の民主化運動の担い手たちが感じていた恐怖を見事に体感させてくれた。
対共分室の露骨な弾圧に比べれば、『新聞記者』で描かれる内閣情報調査室の活動など可愛いものなのかもしれない。警察ではないから物理的な暴力を行使することはないし、していることと言えばネットでデマをまき散らしたり、せいぜい恫喝する程度だから。対共分室が行っていたのは権力を笠に着た明らかな犯罪だが、内調はグレーと言えばそう言えなくもない。
しかし、やっていることの本質は同じで、それは恐怖による支配だ。恐怖が人々の足をすくませる。その恐怖による支配を余すところなく見せつけるという点で、この二つの作品の手法は共通していると思う。
ところが、『1987、ある闘いの真実』は最後に正義が勝つのに対し、『新聞記者』は…。後味の悪さは『新聞記者』のほうが圧倒的に上で、観客はそこで味わった恐怖をそのまま家に持って帰ることになるのだ。
こっちのほうが怖いです、はっきり言って。
望月衣塑子記者の著書とは別物
この映画は“望月衣塑子氏の著書『新聞記者』の映画化!”ということで話題になったような気がするのだが、でき上がった作品は本とはまったくの別物のようだ。読んでいないから偉そうなことは言えないけれど、本のほうは望月氏のジャーナリストとしての半生を綴ったもの。一方映画にはそんな要素は微塵もなかった。映画の主人公は彼女と同じ女性新聞記者だけれど、日韓ハーフでアメリカ育ちという設定からして望月氏とはまったく違うし、演じるのも韓国人女優となれば、本をベースにするつもりなどハナからなかったことが分かる。まあ、製作発表の時点で「原作」ではなく「原案」だとはっきり言っていたので、勘違いしたこちらが悪いんだけど。

これをきっかけに、民主主義と言論の自由を守る戦士として、同調圧力に屈しない自立的な精神の持ち主として、また戦う女性の象徴として、彼女に注目が集まった。政治、言論といった分野で一躍“トガった”存在として認知されるようになったのだ。彼女は非常に分かりやすいやり方で“時代の空気”をかき乱していた。(当人はしんどいに違いないが。)
だから映画の中でも、強い者とのそういう丁々発止のやりとりが見られるのかと期待していたのだが、その期待は外れてしまった。しかし、そんなものよりずっと凄いものを見ることができた。
映画というメディアでできること
権力者に敢然と立ち向かう望月記者は力強いし、僕なんかには自由の女神のようにも見えるのだが、彼女がいくら頑張っても菅長官の愚弄するような態度は変わらないというのが現実だったりする。そして、それは官房長官会見の場だけの話ではない。政権の横暴、抑圧、欺瞞があちこちで露見しているのに、なぜか誰も責任を取ることなく放置されている。世の中はこのまま変わりそうになくて、そのせいで空気そのものがすっかり重苦しくなってしまった。
たぶん、(たぶんだけど)この映画の製作陣は、望月記者よりもっと大きい声を上げようとしたんだろうなと思う。(ここからは妄想です。)
 左が河村光庸プロデューサー、右が藤井道人監督
左が河村光庸プロデューサー、右が藤井道人監督新聞記者にできることには限りがある。会見で鋭く問い詰める。取材をする。そして記事を書く。しかし書けるのは事実だけだ。いま望月記者がジャーナリストとして日夜実践していることを、同じマインドを持って映画でやるとしたら何ができるか…。そんなふうに考えたのではなかろうか。
あえて「フィクション」にしてまったく別の物語に仕立てるという発想も、そういう気概から生まれたものではないだろうか。映像化するだけでもインパクトと波及力は格段に高まるはずだが、「事実」という制約にとらわれなければ表現の幅が大きく広がる。エンターテインメントとしてのクオリティはそのほうが高められるという自信があったのだろう。
だから、ここまで変わり果てた作品にしておきながら望月記者の本を“原案”と言い張るのは、意地悪な言い方をすれば、「望月衣塑子」のネームバリューと、自由の戦士、空気の破壊者という彼女のイメージを利用したかったのだろうし、それはすなわち、彼女と同じマインドでこの映画を作るという宣言でもあるのかなと思う。そのマインドがこの映画の原型になっていると。
(妄想終わり。)
内閣情報調査室
望月記者は日々戦っている。相手は菅官房長官、内閣記者会(記者クラブ)、彼女が記者として追うさまざまな問題の(権力側の)当事者たちと多岐に渡るが、それでも生身の人間である以上、戦える相手の数は限られている。基本的には自分が直接対峙できる相手としか戦えない。もちろんペンの力というものもあるけれど、それにしたって自分が見据えている相手としか戦えない。
映画の製作陣はその限界から抜け出したかったんだろうと思う。
菅長官の態度は言語道断だが、言語道断なことや「なんで?」という疑問を残したまま有耶無耶になっていることは他にもたくさんある。望月記者という一個人から離れて俯瞰することで、またフィクションとして仮説や推測を交えて再構成することで、それらすべてを同じテーブルの上に載せることができる。
(なんかまだ妄想が続いてますが。)
それぞれ脈絡のないものとして人々の記憶に残っているそれらの事件を並べて置く場所、つまりテーブルとしてこの映画が選んだのが、内閣情報調査室という組織だった。すべては内調というテーブルの上に並べることができる——要するにすべてに内調が絡んでいた——という仮説のもとに再構成したのである。
これまで表に出ることがほとんどなかったから、多くの日本人はこの組織を知らない。しかし、「政治の安定」を脅かす人間が現れたとき、あらゆる手を使って芽のうちに摘み取っているのがこの組織なのだ。反政府的な動きは潰し、政権のイメージを傷つける出来事はもみ消す。もちろん他にも仕事はあるのだろうが、汚れ仕事の実行部隊として果たす役割は大きく、政権にとっては頼りになる存在だろう。だから、この組織を知れば“時代の空気”の核心が見えてくる。
もちろん本当に悪い奴らはもっと上にいる。内調をほしいままに操っているのはそういう連中だ。だが、この映画には首相も官房長官も一度も出てこない。いわゆる官邸という言葉でさえ(僕の記憶では)数えるほどしか口にされない。そうした真の権力者=巨悪を追い求めるのではなく、その手前(周囲?)にある巨大な防波堤にカメラの焦点を合わせているのだ。ひたすら内閣情報調査室という組織の実態を暴いていく。
この映画のタイトルは「新聞記者」で、主人公も新聞記者(と内部告発者)で、彼女(と彼)が一つの真実を追い求めるストーリーが物語の軸になってはいるけれど、途中から彼女たちは狂言回しとしか思えなくなってきた。
彼女たちが追う事件も含めて、すべてが内調とつながっていて、つながればつながるほど内調の不気味さが増幅され、存在感が増していく。主人公の二人は好演しているとは思うけれど、存在感という点では圧倒的に内調のほうが上だった。まあ、こんな受け取り方をしたのは僕だけかもしれないけど、映画としてぜんぜんOKだと思うし、それに望月記者のマインドで映画を作るという主旨——と僕が勝手に妄想した——から言えば、大正解だと思う。時代の空気そのものが浮き彫りになってくるし、どんな相手とのどんな戦いを強いられているのかが明らかになってくるからだ。
それにしても内閣情報調査室という組織は本当に不気味な存在で、この映画は一級品のホラー映画だと言っていい。しかもゾンビとかエイリアンではなく実在の組織であり、いつ自分にその手が伸びてくるかもしれない。ゾンビやエイリアンなら映画館から出たら絵空事だと忘れてしまえばいいが、そうもいかないと言うか、そうしてはいけないという話なのだ。
後で少し詳しく触れるけど、この組織のトップを演じた田中哲司の存在感と威圧感が凄まじかった。胸が悪くなるレベルの、超一級品の演技。怖い。
「フィクション」を逆手に取る
米国や韓国の社会派映画はたいていの場合、“事実に基づく物語”であることを謳い文句にしているのだが、この映画はノンフィクション本を「原案」としながらも、まったくのフィクションとして作られている。
ただし「事実に基づく」映画も、すべてが事実の通りに作られるわけではない。物語として成立させるためにかなりの脚色を施しているのが常だろう。観る側はある程度までそれを許容しながら、エンターテインメントとして楽しむ。この映画が面白いのは、かなり意識的にその逆をいっていることだと思う。「フィクション」の体を作るためにわざと細部を変更しながらも、実際に起こったものとほとんど同じ内容の事件が次々に登場する。観る側は“ここが変えてあるな”などと意識しつつ実際の事件を思い浮かべるのだが、これがけっこうワクワクさせてくれる、不思議だけど。いつの間にかノンフィクションとして観ているのと変わらなくなっている。
前川喜平元文科事務次官の出会い系バーのスキャンダルは、不倫スキャンダルに変えられ、次官の名前も変えられているが、文科事務次官のスキャンダルというだけで前川氏の件を思い出さざるを得ない。おまけに全国紙が奇妙な報じ方をしている——すべての地方版で同じ掲載位置、同じ文面——のは、前川氏のときの読売とまったく同じだ。
総理の覚えめでたいジャーナリストのレイプ事件がもみ消されるという話も出てくるが、これに至っては名前以外は伊藤詩織さんの事件そのままと言っていいくらいだ。顔出し記者会見が話題になるところもそうだし、その後猛烈なバッシングが起こったことも現実と同じ。
物語の軸となるのは加計学園問題とよく似た不正事件だし、ほかにも役人による公文書改竄や自殺など、現実に起こった事件を彷彿とさせる出来事が次々に出てくる。そしてそのたびに生々しい記憶がよみがえる。
きわめつけ、というか、「フィクション」という触書を茶化すように挿入されているのが、実在の人物によるディスカッションの場面だ。あろうことか望月衣塑子記者本人が画面に登場する。彼女のほか前川元事務次官、朝日新聞の南彰氏(新聞労連委員長)、元ニューヨークタイムズ東京支局長のマーティン・ファクラー氏が実名で登場し、「官邸権力と報道メディア」について4人で真剣に討論するのだ。

映画で使われたのは上の動画だと思うけど、確信はございません。
⇒画像をクリックするとYouTubeに飛びます。
ディスカッションはネットで同時配信され、「フィクション」の中の登場人物たちがそれぞれの場所でそれを見る。あたかも実在の4人が「フィクション」の中で起こる出来事を論じているように見えて、それを「フィクション」の中にいる人々が視聴するというアクロバティックな構造だ。物語の要所要所で短く、しかし意味のある発言がカットインされる。
これはスゴイなと思った。
もちろん手法としては別に珍しくもないのかもしれない。ドラマや映画の中にテレビが映し出され、その中で実在のアナウンサーがニュースを読むといった光景はよくあるパターンだ。でも、それでリアリティが増したりするわけではなくて、たいていは笑いを誘うだけだろう。しかし、この映画の場合は次元が違う。
4人の話しぶりからして台本があったとは思えない——映画で使うことを前提に企画されたのかどうかも分からないし——のだが、ストーリーの流れに見事に溶け込んでいるだけでなく、彼らの発言は物語と完全にリンクして明確な意味を持ち、「フィクション」の登場人物たちを行動に駆り立てるのだ。
「フィクション」だからこんなことができるんじゃないかな。
それと、これによって主人公の吉岡記者が望月記者とは別人格であることが示される。最初は奇妙な感じがしたけれど、とにかく言っていることが至極まともなので聞き入ってしまった。ちゃんと映画の中の事件の解説・批評になってたし。
要するに、「フィクション」であることを最大限逆手に取って、ノンフィクションに限りなく近い受け取り方を観る側にさせる——この映画はそういう戦略に貫かれているのだと思う。下手をすると安直さをさらけ出すことにもなりかねない手法だと思うが、この映画は不思議なほど成功している。(個人の感想です。)
物 語
軸となるストーリーは、戦略特区制度を利用して進められる大学新設の話。大学設立の主体が総理のお友だちというところが加計問題とそっくりだ。映画のほうは獣医学部ではなく医学部で、その裏に生物兵器開発の計画があるというスケールの大きな話になっている。だが、当然観る側は加計学園を頭に思い浮かべながら観ることになる。
内閣府でその案件に関わったのが神崎という外務省出身の高級官僚で、事の重大さと凶悪さに気づいた神崎は、機密資料の一部を東都新聞に匿名でファックスし、その後自殺する。
登場人物
先に進む前に主要な登場人物について。
シム・ウンギョン演じる吉岡エリカは東都新聞の記者。父は日米で活躍した日本人ジャーナリスト、母は韓国人。しかし二人ともすでに他界している。彼女はアメリカで育ったが、帰国して新聞記者になった。神崎から送られてきた機密情報の裏取りを命じられる。
松坂桃李演じる杉原は外務省の官僚で、今は内閣情報調査室に出向している。自殺した神崎は彼の外務省時代の先輩。5年前、杉原も関わった文書改竄事件の責任を一人で負ってくれたのが神崎だった。(おそらくその結果)神崎は内閣府に出向させられ、特区の仕事をしていたということだろう。
杉原の現在の上司が内閣参事官の多田(田中哲司)で、この人物が内閣情報調査室を動かしている。
内閣情報調査室
ついでに内閣情報調査室についても。
多田の下で杉原がどんな仕事をしているのかというと、一言で言えば公安警察と連携しての情報収集ということになるが、情報を集めて終わりというものではない。ときにそこからデマをでっち上げ、SNSなどを駆使して拡散する。与党ネットサポーターに協力を依頼することもある。また、デモの写真に写った一般人を公安にマークさせたりもする。
レイプもみ消し事件のときも、被害者の記者会見が終わるとすぐに女性への誹謗中傷が調査室から拡散されていった。杉原は女性と野党を結びつけるデマ情報の作成まで担わされた。
また、神崎が自殺すると即座に彼の汚職疑惑のデマがでっち上げられ、それが調査室から拡散された。杉原もその業務に参加させられる。神崎のリークを嗅ぎつけた内調が彼をマークし、それで追い詰められて彼は自殺したのだが、そのことは同じ外務省出身の杉原にはいっさい知らされていなかった。
すべては政権与党を守るための裏工作だった。政府に反旗を翻す者が現れれば、弱みを探し出し、事実であろうとなかろうとそれで脅しをかけて潰す。
多田の口癖は「政治の安定のため」だった。杉原がときに批判的な意見を言うと、いつもその言葉が返ってくる。そして多田は言う。「ウソかホントかを決めるのはオマエじゃない。国民だ。」
窓がなく薄暗いオフィスには整然と机が並んでいる。それぞれの机の上にあるのはPCだけ。職員が帰ったあとは人の痕跡がまったくなくなる。無機質。勤務時間中は何十人もの職員が黙々とPCのディスプレイに向かい、キーボードを叩く。多くは杉原と同じように各省庁から出向してきたエリート官僚なのだろうが、やっているのはデマのでっち上げとその拡散なのだ。ネトウヨと同じだ。なんとも救いがないが、誰も歯向かうことなく忠実に業務をこなす。
 内調内部の写真はこれしか見つからなかった。
内調内部の写真はこれしか見つからなかった。映画の中でこんなことを言っていた。
破防法の仕事(思想犯案件)がほとんど無くなってしまった公安から、かなりの人数が内調に移されている。なるほどなと思った。だから公安との連携もスムーズにできるし、エゲツないやり方もお手の物なのだ。
再び物語
神崎のリークは匿名だったため、吉岡は取材に行き詰まっていた。だが神崎の死でいろいろな情報がつながり始める。日頃から内調の仕事に疑問を抱いていた杉原の協力も得て、新大学の設立認可の裏にお仲間への利益供与があっただけでなく、設立の真の目的はそこで秘密裏に生物兵器の開発を行うことにあったという、政府与党の驚くべき陰謀が明らかになった。
当然ながら東都新聞には内調から厳しい圧力がかかっていた。報道しても誤報になるぞと脅しをかけてくる。だが、そのときは続報で自分の名前を出していいという杉原の言葉を頼りに、東都新聞は報道に踏み切る。
しかし…。
絶望的な結末
すべてが暴き出されてハッピーエンドで終わるかに見えたが、その寸前で再び闇の中に引き戻され、その瞬間に物語は終わる。まあ、考え得る限りで最悪の終わり方だ。
横断歩道を隔てて吉岡と向かい合った杉原が、口の動きだけで「ごめん」と言い、そこで断ち切られるように映画は終わるのだ。つまり、続報に杉原の名前は載らないということだ。東都新聞のスクープは誤報とされ、内閣情報調査室による日本支配がこれからも続くことが暗示されるわけである。
 ラストシーンの松坂桃李の表情。(これしか見つからなかった。)
ラストシーンの松坂桃李の表情。(これしか見つからなかった。)杉原に対する多田の威圧と懐柔が功を奏したのだ。
考え得る限りで最悪の終わり方ではあるけれど、この映画が描こうとしているものを考えれば、こうなるんだろうなあと思う。これがもっとも効果的なエンディングなんだろうから。内調の不気味さを最大化するには、やっぱりこの終わり方だろう。ほんと、良くできていると思う。
出演者について
主演のシム・ウンギョン(吉岡エリカ役)の演技が高い評価を得ているようだが、僕にはもう一つよく分からなかった。とことんストイックな独特の雰囲気を醸し出していたけれど、その割にあんまり存在感を感じられなくて。父親の亡骸と対面したとき以外、あまり感情を表に出さなかったからだろうか。まあ、僕が鈍感なだけかもしれないけれど。
松坂桃李は(テレビでしか見たことがなかったけど)実はこれまであまり好きではなかった。彼の困ったような笑顔がなんとなく苦手だったのだ。でも今回は良かった。笑うときも泣くときも怒るときも、どこか複雑な感情が混ざり合い、曖昧な表情になる。ラストシーンでは、まったく表情のない青ざめた顔で「ごめん」とつぶやくのだが、そうする自分に自分で絶望しているような痛ましい表情がなんとも言えなかった。絶品。
だが、演技陣の中でもっとも際立っていると感じたのは、内閣参事官の多田を演じた田中哲司だった。怪演と言うべきだろうか。生まれてから一度も汗をかいたことなどなさそうな冷たい表情。デスクからまっすぐに見上げたところを大写しにした顔は、それだけで蛇ににらまれたカエルになったような気分にさせる。ものすごい威圧感であり、存在感だった。
ラスト近くで彼が杉原に言う次の台詞は、この映画の核心とも言っていいものだ。
「この国の民主主義は形だけでいい。」
この言葉はホントにずっしりきた。そう考える人たちが今の日本を牛耳っているんだと思う。
(2019/6/28、7/6イオンシネマ筑紫野にて鑑賞)