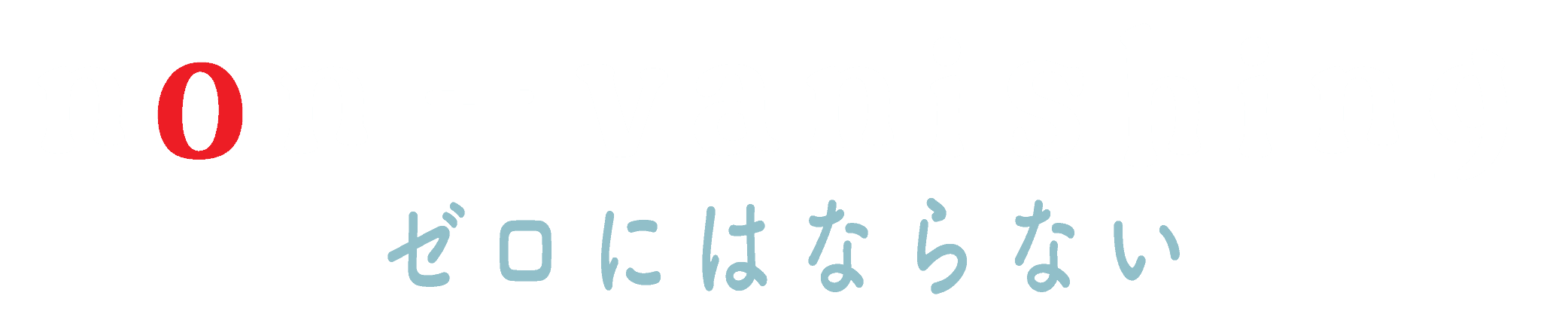安倍晋三首相が国会で云々(うんぬん)をでんでんと読んだ(※1)と聞いたときは「そこまでバカなのか」と思ったし、その道の先輩格である麻生太郎副総理が最近有無(うむ)をゆうむと読んだ(※2)のはニュース映像で見ていたので、「なぜ誰もコイツを引退させない」と思わず声に出してしまった。
ちなみに麻生氏には未曾有をミゾーユーと読むという、おそらくもっと有名で輝かしい過去がある。
この2人に関してはそもそも総理大臣が務まるような能力も器もないと僕は思っている。それどころか、(麻生氏が首相在任期間に何をしたかは覚えていないが、)安倍首相については、東条英機や近衛文麿にも匹敵する歴代最低の首相だと思っている。

だが、それはともかく。
漢字の読み間違いは、仕方ないよなと思う。
僕だってやらかすし。
というか、年を取ると、間違えて覚えてしまった読みをなかなか修正できない。学習能力が落ちてしまったんだろうね。
僕の場合
僕の難敵を紹介すると…
- 場末 バスエ
これは「バスエ」か「バマツ」かいまだに悩む。最初にちゃんと頭に叩き込まなかったのが尾を引いているのだ。出くわすたびに「どっちだったっけ」と辞書を引き、そのたびに今度こそは頭に刻もうと念じるが、だめ。 - 備忘録 ビボウロク
これは読み間違い以前の問題で、「忘備録」と逆さに覚えてしまっていた。音の響きも「ぼうびろく」のほうが自然に感じるんだけど、これは僕だけでしょうね。いまだに覚束ない。 - 固執 コシツ、コシュウ(どちらでも可)
これはなぜか「コシュウ」が正しくて「コシツ」は間違いだと思い込んでいて、ようやく最近になってどっちも間違いではないということが身についた。 - 上意下達 ジョウイカタツ
つい「ゲダツ」と読んでしまう。「上下関係」は「ジョウゲ」と読むだろうが!と刃向かいたくなるんだけれど、『ほぼ日刊イトイ新聞』の「声に出して読めない日本語」に「上司(じょうし)の意見が部下(ぶか)に達する」という説明があって参りました。 - 今上天皇 キンジョウテンノウ
今の天皇を指すことは前後関係ですぐわかるから辞書を引くこともなく、読みも適当に済ませていた。その場その場で「コノエ」とか「コンジョウ」とか。でも最近、それもかえってメンドウだと思って辞書を引き「キンジョウ」と読むことをようやく知った。在位中の天皇を指す一般名詞であることを知ったのもこの時。今という字があるから、それもあるかなと思っていたが、今の天皇の別称か何か、つまり固有名詞の可能性もあるよなとお気軽に考えていた。
こんな感じ。
他にもあると思うけど、思い出せない。
というより、間違いと認識していないものがこの他にたくさんある。間違いなく。
だから、人のことはバカにできない。
人はどうやって漢字の読みを覚えるんだろう?
我々の漢字の知識の核は、小学校から高校の教科書に出てきたもので成り立っていると思う。
漢字力はそれなりに重視されていて、小学校では漢字ドリルというのがあったし、中学校では書取りだけのテストもあり、高校の国語の定期テストにも漢字の出題があった。いずれも教科書に出てきた漢字が対象だった。(だから難問というわけではなかった。)
一方、安倍氏が恥を晒した「云々」も麻生氏の代名詞とも言うべき「未曾有」も、僕が覚束ない「場末」「備忘録」「上意下達」「今上天皇」なども、教科書には出てこなかったような気がする。「有無」と「固執」はあったような気もするけど。
仮にそうだったら、勉強を疎かにしていたとバカにするのは、ちょっと酷だろう。
でも、多くの人がまともな大人なら誰だって知っている常識だと考えているから揶揄するのだ。
じゃあ、みんなどうやってその常識を身につけるのだろう。
親は「辞書を引け」と言っていたが…
正確に比較できるものではないけれど、感覚的には、学校で習う何倍もの数の漢字の読みを、我々は学校の外で覚えるはずだ。常識(教養)の有無はここで決まるんだろうなと思う。
テレビから覚える場合は漢字と音がセットになっているから即座に覚えられるけれど、活字の場合はそうはいかない。
子どもの頃、とくに中学校に上がってからは、知らない漢字を親に尋ねても「辞書を引きなさい」と言ってけっして教えてくれなかった。ひねくれたガキだった僕は、あの人も知らないんだなと決めつけて引き下がったが、子どもが読みたいと思う読み物に出てくる漢字なんて高が知れているわけで、そんなはずはない。
辞書を引く癖をつけさせようと本気で思っていたんだろう。
中学入学時、国語辞典と漢和辞典を買わされた記憶があるから、自分専用の辞書を持っていた。漢和辞典を手に取ればよかったのだ。
でもねえ。
知りたいのは書いてある内容であって、とにかく先を読みたいという思いが強いから、意味がわかれば読みなんてどうでもいいやってなってしまう。
わざわざ辞書を引っぱり出して開く気にはなれなかった。
安倍くんも麻生くんもそうだったんじゃないかな。
あれがいけなかったんだろうねえ。
僕のような怠け者でも本当によく本を読む人だったら、そのうちルビのふってあるケースに出会って覚えられるものもあったかもしれない。ルビで覚えた読みもけっこうあるもんねえ。たぶん「未曾有」を僕が覚えたのはルビからだったと思う。でも、それでは追いつかず…。
取り止めもない話になってきたので、この辺にしておくけれど、今はPCやスマホで読んでいる時は簡単な操作で辞書にあたれるから、便利になったよなあと思う。自分のようなおじいさんも紙の辞書を引くよりデジタルで検索することのほうが多くなった。
とは言っても、デンデンはないよな、デンデンは。ミゾウユウはわからないでもないけど。
※安倍首相
「訂正云々」を「ていせいでんでん」と読み間違い。(2017年1月24日の参院本会議)
※麻生副総理
「文章の有無」を「…もゆうむ」と読み間違い。(2018年3月9日の記者会見)
ちなみに、「うむ」に関してはその後「ゆうむ」とも読むという反論が上がった。それはそれで正しい指摘なのかも知れないが、少なくとも手元にある「福武国語辞典」には「ゆうむ」という項目はないし、「有無」の項に「ゆうむ」とも読むとは書かれていない。それに、麻生氏が両方の読みを知ったうえで「ゆうむ」を選んだとは思えない。(←個人の見解です。)
Wikipediaを覗いてみたら、麻生氏のページには「誤読」という項目がわざわざ設けられていたので笑った。安倍氏のほうは見つからなかったが。