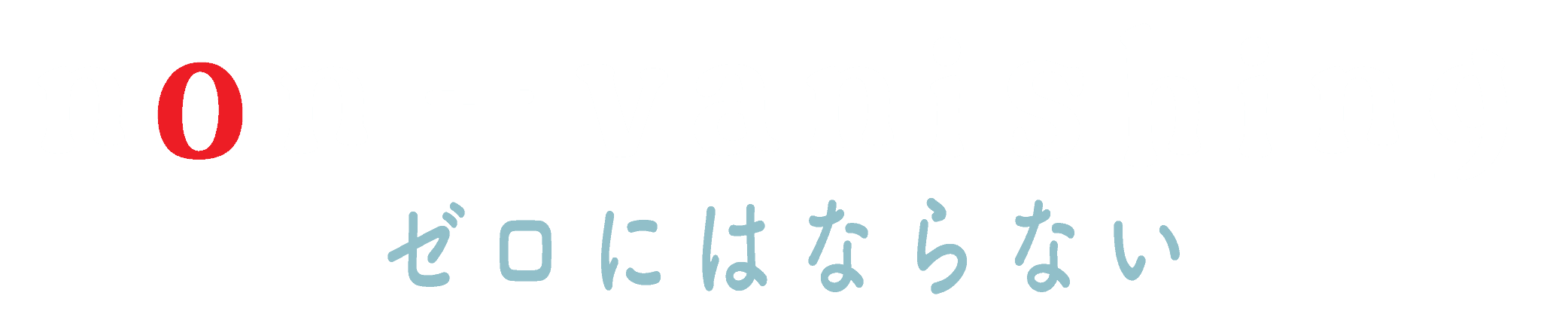実に3年半ぶりの投稿。久々にホームページを開いたらアイキャッチ画像がめちゃくちゃなことになっていたので、一大奮起してWordpressのテーマをブロックエディター対応のものに変え、画像の入れ替えが必要なものは入れ替え、崩れた部分を補修し…で、せっかくだから新規投稿も。
岩井 克人(いわい かつひと)氏は1947年生まれの日本の経済学者(経済理論・法理論・日本経済論)。学位はPh.D.(マサチューセッツ工科大学・1972年)。国際基督教大学特別招聘教授、東京大学名誉教授、公益財団法人東京財団名誉研究員、日本学士院会員。——Wikipedia
この本は、単行本出版が2000年、文庫化が2006年で、手元にあるのは文庫の第4刷(2011年)。2014年の年末に購入したまま読んでなかった。
1985年から1999年にかけて書かれた資本主義経済に関する一般向けエッセイが収録されている。
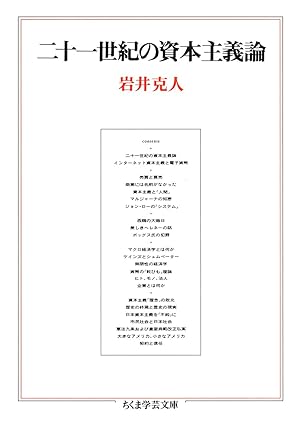
前世紀に書かれたもの——中には40年も前に書かれたものもある——を今さら読むことに意味があるのだろうか?という疑問を抱きながらページを捲りはじめた。経済学の基礎知識さえ持ち合わせていないから、すでに間違いだと確定したことを、有り難がって信奉してしまうかもしれない。
だが、読みはじめると、あっという間に著者の文章力に心酔することになった。こんなに平易な言葉でわかりやすく、そしてリズムよく専門分野の話をすることができるのか。
書かれていることも、資本主義の成り立ちとか、ここがキモだと著者が考えることについてだから、かんたんに過去の遺物として葬り去られるものとは思えなかった。安心してナルホド!と膝を打てる。
でもまあ、本題について書きはじめると長くなるので、ここでは経済からは少し離れた2つのエッセイについて書き留めておく。とても印象に残ったので。
「歴史の終焉と歴史の現実」(1991.4.1)
この年の1月にはじまった湾岸戦争について、まだ交戦中の段階で書かれたエッセイ。
あの戦争については、テレビで見た映像が今でもはっきり記憶に残っている。爆撃機がイラクの軍事施設を爆破する様子で、まるで自分が操縦席に座っているかのように思える映像だった。あるいはゲームでもしているかのような——照準を合わせ、ミサイルだか機関銃だかを発射し、光が超高速で走って見事に命中する…それで終わり。あの先で多数のイラク兵、そして民間人が死傷しているはずだが、それは見えない。戦争のリアルからは程遠く、シンプルかつクリーン。後ろ暗いものは何も残らない。
隣国クウェートに侵攻したイラクに非があることは明らかだった。国連の正式な決議を経て米軍を中心とする多国籍軍が組織され、攻撃を開始。
今では奇跡のように思えるが、米ソが歩調を合わせ、アラブ諸国も口を出さなかった。いや、口を出さないどころかアラブ世界からも多くの国が多国籍軍に参加した。それほど善と悪がはっきりしていたということだろう。
しかし、著者はこの「勧善懲悪的な結末が、『歴史』というものにかんするひとつの誤謬にみちた物語をひとびとの心に定着させてしまうことにたいする恐怖」(P317)を感じると書いている。
1991年といえば、東欧の社会主義体制が崩壊した直後である。自由主義陣営の勝利、資本主義の勝利が誇らしげに叫ばれていた。
「歴史の終焉」というフレーズが日本の片田舎に住む僕の耳にも聞こえてきた。
「自由の理念の実現を目的(end)としてきた歴史(history)があのベルリンの壁とともに終焉(end)してしまったという物語(story)」(P318)。
湾岸戦争は、西欧社会からはその「歴史の終焉」の仕上げ作業に見えただろうと著者は言う。
しかし、西欧社会の外に住む人々には違った見え方をしているはずだと。
西欧社会に対する反発にしっかりと目を向けるべき
西欧社会においてひろく流布しているこのような勧善懲悪的な構図にたいして、アラブ諸国だけでなくアジアやアフリカの多くの発展途上国においては、この湾岸戦争を異なった宗教、異なった文明、異なった価値、異なった歴史のあいだの衝突の象徴とみなす意識が次第に強くなってきている。
(中略)
アメリカを中心とする多国籍軍がイラクを軍事的にたたけばたたくほど、西欧社会に対する反発がこれらの地域における民衆意識の底流として強まっていくのである。
(中略)
「歴史の終焉」を完成させるはずの多国籍軍側の軍事的な勝利は、皮肉なことにその「歴史の終焉」をさらに引き延ばす効果をもつことになるだろう。(P318〜319)
湾岸戦争は誰もが予想したように短期間で終了したが、10年後の9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が起こったことを我々は知っている。テロリズムを肯定する気はさらさらないが、著者が言うように、西欧社会に対する反発が非西欧世界の民衆の中にマグマのように溜まっていたことが最悪の形で証明されてしまった。
しかも、そこからアフガニスタン紛争、イラク戦争というアメリカによる報復がはじまるが、後者は周知のように誤情報に基づく——つまり根拠のない——攻撃だったことが後に明らかになった。反米、反西洋の意識はさらに強まっていると考えていいだろう。
ある種の祝祭気分さえ漂っていたあの時期に、抑圧されてきた民族の心中を的確に言い当てた著者の慧眼に驚かされた。
「憲法九条および皇室典範改正私案」(1996.8.9)
朝日新聞フォーラム二十一委員として寄稿を依頼されて書いたものの、掲載を拒否されたという曰くつきのエッセイ。その後、文字量を減らすなどの条件付きで掲載されたというが、この本には当初の原稿が収録されている。
憲法九条については、日本国民は、1.自らの防衛、2.国連の指揮下にある平和維持活動、3,内外の災害救助、の三つの目的にその活動を限定した軍隊を保持することを世界に明言した内容に改正します。
皇室典範については、1.皇族は男女ともに皇位継承の資格をもち、2.皇位継承資格者はその資格を放棄する権利をもち、3.天皇自身も自らの意思で皇位を退く権利をもつ、と言う内容に改正します。
皇位継承の資格を放棄した旧皇族は、一国民として、参政権をはじめとするすべての市民権を享受しうることになります。(P338)
日本国憲法と同じ1947年に生まれた著者は、憲法9条を「人類の未来を先取りした平和思想の表明として、誇るべき日本の財産」(P340)だと長い間考えてきた。しかし、冷戦が終了した今、すべての国の国民は世界市民としての「責任」を負わざるをえないとして、このような提案をしているのである。
9条の改正案そのものは、それほど目新しいものではない。国連の機能不全が明らかになった今となっては、2の持つ意味は当時と異なるだろうが、このように目的(歯止め)を明示したうえで武力の保持を条文化するのであれば、多くの国民が賛同するのではないかと思う。
ついでに言っておくと、今改憲に反対している人たちの多くは、再び好戦的な国家に成り果てる可能性を封じるために反対しているのだ。
自衛隊が現に存在することで9条がすでに空文化していることは、子どもにだって分かる。本来なら自衛隊を解散するか、9条を改正するか、どちらかをすぐにでも選択すべきだ。しかし、少なくとも大日本帝国の過ちに正面から向き合おうともせず、神道の復権を許そうとしている歴史修正主義者たちのリードでこの議論を進めるわけにはいかない——そう考えているのである。
だが、著者はもっと根源的なところから議論をはじめる。象徴天皇制が孕む矛盾である。
国民が主権者であることを再確認するために
「問題はこの憲法上の規定と現実の天皇制との大きな乖離です。」(P342)
昨日までの現人神が新憲法の施行によって「日本国の象徴」に変わった。しかし、天皇と呼ばれる人は昨日も今日も同じ人物だった。
主権は国民にあり、天皇の地位は「国民の総意に基く」と言われても、少なくとも1000年以上の間、天皇の称号を代々受け継いできた家系の家長が昨日も今日もその地位にあるわけで…。
日本人はこの変更をうまく受け入れられずにいる、と著者は考えているようだ。
私たちは、過去のみならず現在においても、自分たちがその天皇に対して主権者であるという意識を持てない。今の象徴天皇制は、私たちの意思を象徴するどころか、私たちが自分で自分の国の運命を選べないことのまさに象徴となっているのです。(P342)
そして、これは、「天皇自身が天皇であることを選ぶことができないということと表裏一体」をなしていると言う。
国民が自らの運命を選べないことと、天皇が天皇であることを選べないこととは、合わせ鏡のように互いの主体性の不可能を映し合っているのです。
ここに真の意味での無責任体系が成立します。
(中略)
今の日本の中心に一つの空洞があります。それは、自らは主権を奪われ、他からは主権を奪う構造的な空洞です。(P343)
正直なところ、国民が自分たちを主権者だと思えずにいるというところまでは分かるが、そのことと、天皇が天皇であることを選べないこととが合わせ鏡だという点は今ひとつピンとこない。
とはいえ、いずれにしても著者が言いたいのは、今の日本のように誰も主権者意識を持っていない無責任な国に武力を保持する資格はないということだろう。
そうさせているのは、(よく分からんけど)敗戦後に生まれた新しい天皇制が、日本の主権を透明化してしまっているからだと著者は考えているようだ。
一番分からないのは、では何故、天皇自身が天皇であることを選ぶことができるようになればそこから脱することができると言えるのかという点だが…。
厳格すぎる——しかもお妾でも持たないかぎり近いうちに瓦解するに違いない——世襲制を廃し、自ら希望して即位した天皇を戴くことができれば、日本国民は自らを主権者だと自覚することができる…のか?
やっぱりよく分からないが、大日本帝国憲法下でそうであったように、今も日本は気味の悪い無責任体系を抱え持っているというのは直感的に理解できる。そして、その状態のまま戦争をできる国になってはならないということも。
こういう主張はこれまで聞いたことがなかった。
どこかの国が攻めてきたらとか、台湾有事がどうのとか言う前に、あれだけの過ちを犯したこの国が再び武力を持つにはどんな自己改革が必要かを考え、実行しなければならない——この指摘には心から賛同する。