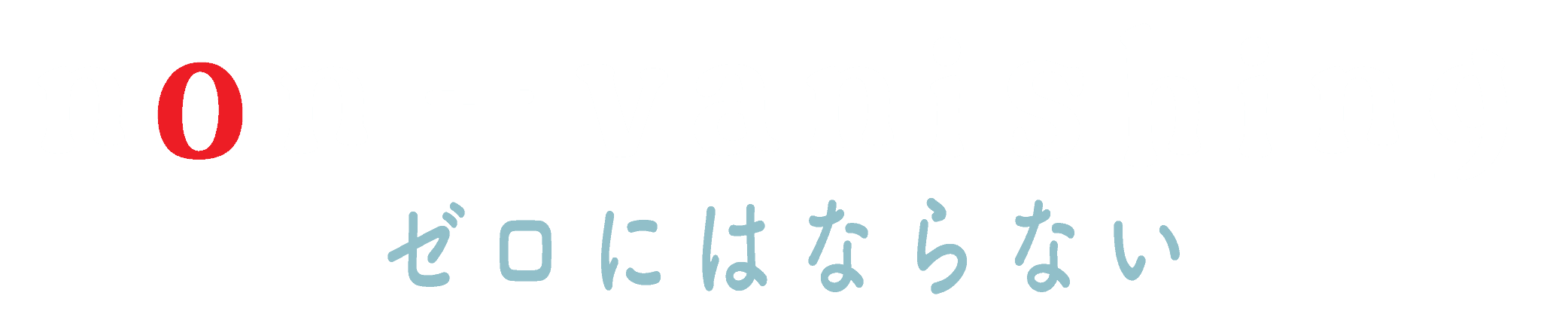この本の概略は裏表紙の説明文がわかりやすい。(新潮文庫)
「早く死ね、自分で死ね。」2003年、全国で初めて「教師によるいじめ」と認定される体罰事件が福岡で起きた。地元の新聞報道をきっかけに、担当教諭は『史上最悪の殺人教師』と呼ばれ、停職処分になる。児童側はさらに民事裁判を起こし、舞台は法廷へ。正義の鉄槌が下るはずだったが、待ち受けていたのは予想だにしない展開と、驚愕の事実であった。第六回新潮ドキュメント賞受賞。
(裏表紙)
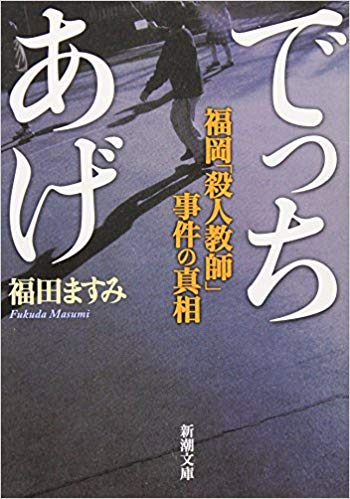
信じられないほどの大どんでん返し
事件
「事件」とされたこと
小学校の教師が自分のクラスの児童に対し、アメリカ人の血が流れているという理由で差別的な言動を繰り返し、たび重なる体罰で児童は何度も怪我を負ったとされるショッキングな「事件」。教師が発したとされた差別発言はカルト的排外主義者でも言わないような低劣なもの。体罰も、もし誇張がないのならば怪我を負わせることが目的だったと思わざるをえないものだった。福岡で起きたことなのになぜか僕の記憶には残っていなかったのだが、ワイドショーなどでも取り上げられて全国を驚かせたらしい。
児童の親が抗議
親の抗議を学校側はすぐに受け入れて教師に謝罪させたが、両親の怒りはおさまるどころかどんどんエスカレートしていった。学校側はその後も教師に対して、監視のために校長や教頭が授業に張り付く⇒担任からはずす⇒研修所送りにするという具合に、親の勢いに押される形で指導を強めていく。市の教育委員会も停職6カ月という異例とも言える重さの懲戒処分を科した。学校も教育委員会も親の言い分を100%認めて教師を罰したことになる。
マスコミの反応
マスコミの報道も苛烈を極めた。地元紙や地元テレビ局はもちろん全国紙、全国ネットのワイドショーでも取り上げられ、いずれも親の言い分を鵜呑みにして教師は極悪人扱いだった。極めつけは週刊文春で、実名と顔写真、自宅写真まで載せたうえで、「『死に方教えたろか』と教え子を恫喝した史上最悪の『殺人教師』」と題して煽り立てた。
裁判
民事裁判へ
しかし、それでも両親は気がすまず、民事裁判を起こす。児童は教師によるいじめが原因で重篤なPTSDを発症したとされ、人権派弁護士550人による大弁護団が結成されるという驚くべき展開で裁判は幕を開けた。しかし…。
裁判で明らかになったこと
裁判で明らかになったのは、一言で言えば、親のウソだった。
もちろん児童本人のウソもあったのだろうと思う。だとしても、学校側も教育委員会も550人の大弁護団も事実認定がまったくできていなかったのは確かだ。訴状に並べ立てられた教師の悪行は、どれも「いつ」「どこで」行われた行為か曖昧で、裁判が進むにしたがってリアリティを失っていく。
それだけではない。児童がPTSDに苦しんでいるという診断にさえ疑問が呈された。長く入院しているとはいえ、カルテには症状が現れたことを示す記載がまったくなく、それどころか186日の入院期間中106日も外泊しているのだ。そして土日には毎週のようにサッカーの練習のため小学校の校庭に元気な姿を見せている。PTSDを発症するほどのひどいイジメにあった、その学校の校庭に。
それぞれの主張と裁判所の判断
Wikipediaの「福岡市『教師によるいじめ』事件」に各当事者の主張・判断が掲載されているので引用する。「人事委」とは、停職処分に対して教師が起こした不服申し立てを審理した福岡市の機関で、裁判と直接の関係はない。
教諭の主張および福岡市・裁判所の判断
上記児童らの主張に対する教諭の反論、福岡市教育委員会(2003年8月22日)、福岡高等裁判所(2008年11月25日)、福岡市人事委員会(2013年1月17日)の判断は以下のとおりである。
児童らの主張 教諭の主張 市教委の判断 裁判所の判断 人事委の判断 「血が混ざっている」発言 認める 認められる 判断せず 認められる 家庭訪問中の差別発言 否定 認められない 認められない 児童らの主張は「虚偽というべきである」 学校での体罰 否定 認められる 判断せず 認められない 体罰による怪我 否定 認められない 認められない 認められない 授業中の差別発言(1) 否定 認められる 判断せず 認められない 授業中の差別発言(2) 否定 認められない 認められない 認められない 児童の持ち物をごみ箱に捨てた行為 ランドセルをごみ箱の上に置いただけ ランドセルをごみ箱の上に置いた、ないし中に入れた 床に落ちていたランドセルを拾い、持ち主は取りに来るように呼びかけた上、ごみ箱に捨てた ランドセルをごみ箱に入れた(指導目的) 自殺強要発言 否定 審査せず 認められない 審査せず 児童のPTSD 否定 審査せず 認められない 審査せず
- 人事委員会は、教諭が児童のランドセルをごみ箱に入れた行為は、いじめではなく教育指導目的と認定。ただし、指導としても行き過ぎであると述べた。
- 裁判所が「判断せず」とした項目は、被告福岡市が自白したために、証拠調べによる事実認定の対象にならなかったことによる。
- 市教委が「審査せず」とした項目は、懲戒処分の直前ないし処分後に児童らから主張されたものであるため。
- 人事委が「審査せず」とした項目は、当該項目が審査の対象である懲戒処分の処分理由に含まれていないことによる。
(Wikipedia「福岡市『教師によるいじめ』事件」)
こうして並べてみるとまったくヒドいとしか言いようがない。上の表も主にこの本を含めた福田の著述をソースとしてまとめたものなので、その点は注意が必要かもしれないが、両親の訴えがことごとく退けられていることに驚く。また表下の注にもあるように、裁判所が「判断せず」としたのは、福岡市が事実と認め、裁判で争わなかった事項である。争っていたらどうなっていたかはわからない。と言うのも、裁判後の人事委の判断では、争点としなかった事項のうち「血が混ざっている」発言以外はすべて否定されたからである。
ちなみに、報道が全国規模に広がる火付け役となったのが週刊文春の記事だったが、そこでセンセーショナルに取り上げられた虐待行為は、いずれも事実とは認められなかった。
判決
一審の判決は、被告の福岡市に220万円の支払いを求めるもの。その他の原告の請求はすべて棄却された。控訴審で賠償額が330万円に引き上げられるが、そこで確定する。(教師については国家賠償法によって免責。)
この判決の受けとめ方も、見る人によって異なってくる。原告からの請求額は最終的には5,400万円という高額に上った(当初は1,300万円)のだが、その1割にも満たないとはいえ「教師による不正行為が認められた」と取るか、あるいは、「裁判所が認めたのは福岡市が事実認定を争わなかった点だけ」だと取るか。この本の著者は後者の見方をしているわけである。また、教師の陳述にも曖昧で整合性を欠いたところがあったとも言う。
結局のところ、双方の弁護団が勝訴をアピールすることになる。裏を返せば玉虫色の判決だったということだ。
しかし、南谷と上村は、専門家の立場から、表向きの認定理由よりも、その背後にある裁判ならではの特殊な事情が判決を左右したことを見抜いていた。
裁判官は、被告である福岡市が、すでに、川上の体罰やいじめを認定し、停職6か月という懲戒処分を行っていることを重視したのである。判決内容も、ほぼ福岡市の言い分に沿った形になった。つまり、裁判官は、福岡市の認定について踏み込んで吟味することを避け、無難なところで決着をしたというのが、南谷と上村の見方である。
「双方の顔を立てた示談的な判決だ。一番嫌なパターンになった」
(P279)
懲戒処分の取り消し
2013年1月、福岡市人事委員会が教師に対する懲戒処分をすべて取り消す旨の裁決を下した。教師は、停職6か月という懲戒処分が決定してから約2カ月後の2003年10月、その取り消しを求めて審査請求を行っていたが、審理は裁判の間中断されていたのだ。人事委の最終判断は上記の「教師の主張および福岡市・裁判所の判断」にあるとおり。実に10年ぶりに完全に汚名が晴らされたのだ。
真実は分からないことのほうが多い、たぶん。
最初の騒ぎようと最終決着との間の落差には驚きしか感じない。「判決」のところにも書いたように、見る人によってその「最終決着」の解釈が分かれるのも事実だが、最初に児童の両親が訴えたような犯罪的な行為がなかったことは誰もが認めざるをえないだろう。つまり冤罪なのである、これは。
原告への配慮も必要だが
裁判というもの
ネットでこの事件を検索すると、この本と著者、当該教師、市教委に対する批判(というより罵詈雑言)も数多く見られる。体罰事件の論考に特化したサイトもあって、そこでは被害者(とされる)側の視点から、憎しみに満ちた言葉でこの事件が語られている。この人たちにとっては、この裁判では不当な判決が下されたことになる。
僕自身、裁判所の判断がいつも正しいとは思っていない。裁判というのは、初めに「何を争うか」を決め、それを「何で判断するか」を示して、その範囲を厳格に守ったときにどう判断するのが妥当かを決めるものだ。こう言うと怒られるかもしれないが、絶対的な真理や正義を一義的に追い求めるものではない。一番重視されるのは「厳正」であることではなかろうか。それが真理や正義への近道だという考えなのだろうけれど。
この事件でも「判断せず」とされた事項があった。福岡市があらかじめ裁判では「争わない」と決めたこと、つまり事実と認めてしまった事柄だ。最終的にその中には事実でなかったものもあったことを福岡市自身が認めているのだが、それは裁判が終わってからのことだった。つまり、裁判は福岡市の誤認をベースに設定された「何を争うか」の土俵の中で進められたのだ。これが真の正義だとは言えないだろう。厳正な手続きに従ったことは認めるけれど、結局それが玉虫色の判決を生んだとも考えられる。
このケースでは被告(教師)側に不利な方向に厳正さが発揮されたわけだが、目に見えないところで原告(児童)側に不利な方向に働いたものもあったかもしれない。「何を争うか」と「何で判断するか」が少しでも違っていたら、違う結果に至った可能性は十分にある。
しかし、そうしたことに思いを巡らせてみたとしても、この裁判によって事実が不当にねじ曲げられたとは考えられない。事実をねじ曲げていたのは原告のほうで、裁判によってそのねじれが解きほぐされたと考えるほうが自然だろう。
原告親子
それにしても信じられないようなどんでん返しである。
裁判所の判断をベースにして原告親子を評するとなると、口にするのもはばかれるような表現にならざるをえない。(個人としての評価ですが。)
- 母親は病気としか思えない。虚言癖とか妄想癖という言葉では言い尽くせないものを感じる。学校側、マスコミ、弁護団、医師など、大の大人がことごとく彼女の言葉を信じたことを考えると、本人にもウソをついているという認識がないのだろうと思う。
- 児童本人は、最大限に好意的な解釈をしても「問題児」と言わざるをえない。同級生に対してもしばしば暴力的だし、教師の言うことを聞かない。かなりひどい虚言癖があるのも間違いなさそうだが、自分のウソに整合性をとろうとする様子がまったくないところに病的なものを感じてしまう。少なくともただの嘘つきではない。また、相手によって態度を豹変させる傾向(これは一定の能力がないとできないだろうが)があるので、対応には手を焼くだろう。
- 父親についてはよく分からない。この本ではかなり威圧的な人物として描かれているが、母親や児童の特異さに比べると、よく見かけるタイプと思えなくもない。ただ、母親や児童の言うことに疑問を抱くことはなかったのかと不思議には思う。
こんな感じで、どうしても人格を攻撃するような表現になってしまう。もしも誤解だったら申しわけないが、裁判で明らかになったことを踏まえると、程度の差はあれ、こういう評価にならざるをえないだろう。認識の違い、解釈の違いで生じるような齟齬ではない。彼らは手に負えない悪ガキとモンスター・ペアレンツに他ならず、この事件は、彼らが引き起こした一方的な暴力事件だと考えなければ理解できない。
この3人の人権を慮ってこれらの点をうやむやにすると、今度は教師の人権が侵害されてしまう。というか、教師は事件の発覚以来とてつもない人権侵害を受けてきたわけだし、間違いなく一生消えない心の傷をすでに負っているのだ。「殺人教師」とまで言われたのだから。理性的な人間同士の利害の対立と考えてしまうと、とても辻褄が合わない。
事実確認の欠落
事実がどうだったかの前に、この事件ではあまりにも事実確認がおろそかにされすぎたと言わざるをえない。
学校
最初に児童の両親から抗議を受けた校長や教頭は、親の興奮を静めることに目を奪われ、対策を講じることしか考えなかった。責任問題も頭にチラついただろう。二人が傷口を最小限にとどめようと悪戦苦闘しているのに、そしてそれは教師本人の傷を小さくすることでもあるのに、抗議内容を否定する教師の態度はすべてを台無しにするものとしか映らなかったのかもしれない。
マスコミ
マスコミもひどかった。初期情報があまりにもセンセーショナルな内容だったため、正義感が先に立ってしまったのだろうか。母親の虚言は常識を大きく越えるものだったが、学校側が(確認もせずに)それを追認し、さらに久留米大学の専門医が児童にPTSDの診断を下したため、疑うという発想が生まれなかったのかもしれない。とくに診断の影響は大きかっただろう。原因となる外傷がないのに「心的外傷後ストレス障害」を発症するはずがないという思い込みが生まれ、裏取りの必要性が頭から飛んでしまった記者が多かったのだ。
医師
診断書についても付け加えておく。公判の中で別の専門医によって指摘されるのだが、この久留米大学の診断も母親の言い分に振り回された可能性がある。「心的外傷」についても、その後の「ストレス障害」についても、児童との直接の対話や観察よりも母親の証言が優先されてしまったと考えられるのだ。ここでも事実確認がおろそかにされている。
弁護士
しかし、さらにバカじゃないかと思うのは弁護士たちだ。記者はスピードを求められる。もちろん、だから間違ってもいいというわけではないが、つねに誤報のリスクと隣り合わせであることは理解できる。精神科の医師も仮病を見抜くのはなかなか難しいだろう。とくに強力な証人がいる場合には。でも、弁護士は市と教師を相手取った訴状を書いたのだよ、訴状を。それによって相手の違法性を糾弾し、ペナルティを科すという、国家権力に関わる行為なのに。目を疑うような凶悪な暴力行為を並べ立てながらも、どれ一つとして「いつ」「どこで」行われた行為か確定できてないって…。そんな伝聞情報だけで裁判が成り立つと思えたのだろうか。そこが分からない。550人も弁護士がいて。
並み居る専門家たちがことごとく「何があったのか」をスルーしてしまった。それだけ母親の虚言がウルトラ級であったということでもあるが。
『羅生門』的世界
判決はびっくりするほど原告のウソを暴き、明確に否定した。こんなことは珍しいのではなかろうか。(知らんけど。)
でも、裁判所の判断が真実であるとも限らない。前にも書いたように、テーブルに載せられた材料だけで判断すればという条件付きで、もっとも合理的と思われる判断を示すだけだ。
実際、母親が話したことも教師が話したことも、事実か否かは本人にしか分からない。もし児童にしか聞こえないような声で教師が差別発言をしていたら、あるいは誰も見ていないところで暴力をふるっていたら、当事者の二人にしか分からない。
証拠なんて、存在しない場合のほうが多いのかもしれないと思った。当事者たちにしか知りえないことがあまりにも多い。であれば、第三者による合理的な判断にそれほど高い精度は望めない。
この事件の場合は、母親の虚言が異常としか言いようのないものだった。最初はそのためにみんなが騙されたけれど、あまりに多くの綻びが露呈して信憑性を失った。でも、あそこまで病的でなかったらどうだっただろう。冷静な悪意に基づき、初めから教師を陥れようと周到に用意されていたら…。
いや、そこまで極端なケースでなくとも、保身のためにどちらかが、あるいは双方がちょっとしたウソをつくことなんてざらにある。それどころか、同じものを見たり聞いたりしても人によって解釈が異なるなんてことはよくあることだ。
まさに映画『羅生門』の世界。
真実なんて分からないことのほうがたぶん多い。それを肝に銘じるべきなのだ。だから、冤罪なんていくらでも起こるということも。