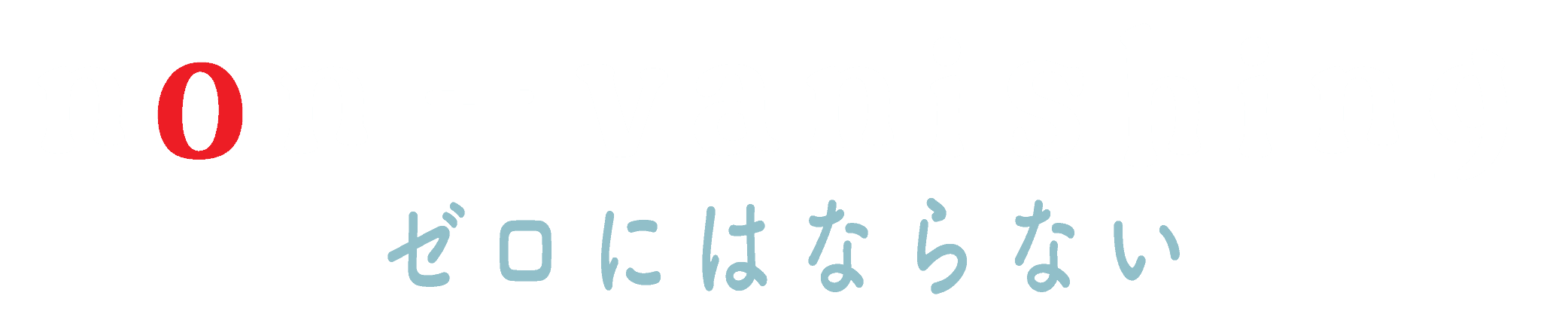著者の松村圭一郎氏は長年エチオピアのフィールドワークを続けてきた文化人類学者。日本とエチオピアを行き来する中で感じてきた違和感を考察し、改めて今の日本を見つめ直したのがこの本だと言える。
「交換(経済)」と「贈与(非経済)」
人が誰かとモノのやりとりをする方法にはこの二種類があって、同一のモノであっても、交換の場合は「商品」、贈与の場合は「贈り物」として扱われる。
考えてみればとても不思議な区別を(それほど深く考えることもなく)我々はしている。
「商品」と「贈り物」とでは意味合いがまったく違ってくるからだ。

「交換」と「贈与」の違い
「交換(経済)」と「贈与(非経済)」とで何が違うかというと、著者によると「思い」とか「感情」が伴うかどうか。
「交換」ではお店から購入者に商品の所有権が移るが、そこに「思い」や「感情」は必要ない。商品と引き替えに買い主が代金を支払えば、それでやりとりは完了する。店員は最高の笑顔を浮かべるかもしれないが、それは職業上の所作であって、客に対する個人的な感情を表現するものではない。
一方プレゼント(「贈与」)の場合、同じように贈る側から受け取る側にモノの所有権が移るが、代金は請求されない。返礼は期待されるものの、それはお金ではない。非経済行為にお金が介在してはいけないのだ。「贈り物」はモノにではなく、贈る側がそれに託した「思い」や「感情」にこそ意味がある。だからお金には換算できない。思いや感情を受けとめ、それに返礼しなければならない。
こんなふうに言うこともできる。「交換(経済)」には個人的な人間関係は必要ない。店員と客が親しく会話を交わすことはあっても、赤の他人のままでいい。むしろそのほうがスムースに行く。等価のモノ(この場合はモノと代金)を交換することこそが重要なのであって、それ以外のこと——人間関係とか感情とか——は余計なことなのだ。だからできる限り排除される。経済行為は脱感情化されることで成り立っている。代金さえ支払えば人格が問われることさえもない。
「贈与(非経済)」はまったく逆だ。贈与とは思いや感情の表現そのものであり、ほとんどの場合、人間関係が前提となっている。物乞いへの施しなど例外はあるが、基本的に赤の他人にプレゼントはしない。そして、そこでは「経済」や「お金」が邪魔をする。「経済」とか「お金」の臭いがすると思いや感情が減殺されると信じ込んでいるかのようだ。だから徹底的に排除される。値札を外し、きれいにラッピングするのは、「商品」ではないことをアピールするためだ。贈り物がお金である場合でも、祝儀袋や香典袋の中に丁寧に包み込まれる。
日本社会は「交換」が幅を利かせる社会
著者によると、エチオピア人はよく物乞いにお金を渡すそうだ。日本人を始めとする裕福な外国人は躊躇してしまうことが多いのに、貧しいエチオピア人たちはためらわずに分け与える。それを見て著者は気づく。
いかにぼくらが「交換のモード」に縛られているのかと。
いまの日本の社会では、商品交換が幅を利かせている。さまざまなモノのやりとりが、しだいに交換のモードに繰り入れられてきた。それは、面倒な贈与を回避し、自分だけの利益を確保することを可能にする。やっかいな思いや感情に振り回されることもなくなる。
しかし、この交換は、人間の大切な能力を覆い隠してしまう。
(P34)
なるほどそうだよな、と思う。お金が万能になるって、こういうことでもある。もちろん交換とかお金だけの問題ではなくて、社会全体が構造的にそういう方向へ向かっているわけだけれど、実際「交換のモード」がふつうになってしまったのは確かだろう。だから「贈与のモード」のスイッチがなかなか入れられない。
日本では、自然と感情を生じさせるような状況が社会から排除されている。(中略)それは人と人とのやりとりを「経済化=商品交換化」してきた結果でもある。
商品交換は、やりとりの関係を一回で完結/精算させる。「負い目」や「感謝」といったモノのやりとりに生じやすい思いや感情は「なかったこと」にされる。そこで対面する「人」は、脱感情化された交換相手でしかない。与えるべきものを与え、もらうものをもらったら、その関係は終わる。この交換の関係は、コミュニケーションの基礎となる「共感」を抑圧する。
(P58)
「贈与のモード」のスイッチが入れられないということは、共感を封じ込め、コミュニケーションの可能性を奪うことでもある。
「公平=フェア」な世界
著者の思考の一番の核にあるのは「公平性」である。
終章で、「よりよい社会/世界があるとしたら、どんな場所なのか」という問いを立て、著者はこう答える。
つまり、ひとことで言えば、「公平=フェア」な場なのだと思う。(P165)
本のタイトルにある「うしろめたさ」も、そこから来ている。
エチオピアで物乞いに遭遇したときに発動される「交換のモード」がどういう機能を持つかというと…
ぼくらがたんに日本に生まれたという理由で彼らより豊かな生活をしているという「うしろめたさ」を覆い隠す。そして物乞いになにもわたさないことを正当化する。交換のモードでは、モノを受けとらないかぎり、与える理由はないのだから。心にわきあがる感情に従う必要はないのだから。
(P36)
しかし。人類は元々どういう社会の中で生きてきたかというと…
人類学者が研究してきた狩猟採集民たちは、猟で獲った肉をみんなに分け与える。そのとき、獲物を手にした狩人は謙虚な態度をとる。決して手柄を自慢したりしない。肉をもらう側は礼も述べず、あたりまえのように受け取る。大きな動物を獲った狩人は、しばらく猟を休んで次はもらう側にまわる。わざわざ他人の道具で猟をして道具の所有者にも肉を渡す。誰かが一方的に与え手や受け手にならないよう、慎重に配慮している。「負い目」の蓄積が格差をもたらすことを、ちゃんとわかっているのだ。
(P187)
「交換のモード」に縛られて生きていると、この感覚と知恵が失われていく。と言うか、現代人はこの感覚をすっかり忘れようとしている。著者が言いたいのはそういうことだ。
取り戻せる
我々は「交換のモード」から逃れられないわけではない。
「交換の関係」もべつに絶対的なものでもなければ、固定的なものでもない。血縁を別にすれば、人と人との「関係」が最初から存在するなんてことはあるはずがなく、モノや言葉をやりとりするうちに徐々に形作られていくものだ。関係が行為を生むのではなく、小さな行為(やりとり)の積み重ねが関係を生む。そして、社会とはそういう関係の束なのだ。だから自分たちの行為、つまり他者とのモノや言葉のやりとりの仕方を変えていくことで社会を変えることができる。(P82〜84)
まず、知らないうちに目を背け、いろんな理由をつけて不均衡を正当化していることに自覚的になること。そして、ぼくらのなかの「うしろめたさ」を起動しやすい状態にすること。人との格差に対してわきあがる「うしろめたさ」という自責の感情は、公平さを取り戻す動きを活性化させる。そこに、ある種の倫理性が宿る。(P174)
話題は「国家」「市場」「食料援助」へと大きく広がっていく。
エチオピアはかつて社会主義政権の時代があって、国民は市場経済(資本主義)と計画経済(社会主義)の双方を経験している。これにまつわる記述も興味深かったが、ここでは深入りしない。
ただ、次の記述だけは記録として残しておきたい。脈絡がなくなってしまうが、この本で一番印象的だったから。
もちろん、特定の価値選択へと個人を誘導する仕掛けがたくさん潜んでいる。沖縄在住の政治学者ダグラス・ラミスは言う。芋とかニンジンとか大豆とか豆腐とか、日々の生活に不可欠なもののコマーシャルはない。コマーシャルは、基本的にいらないものを買うように消費者を説得するためのものだ、と。この誘惑の構造が、市場を動かす力になっている。
(P130)
それに市場では、公平とはほど遠い偏った富の配分がなされる。生まれつき多くの財産をもつ人となにももたない人が、その格差を市場のなかだけで埋めるのは至難の業だ。市場で価値あるものを手に入れるためにそれと交換する財をもたない人は、まず自分自身の身体を「労働力」として売るしかない。子どもや病人など、それができない人は、誰かに与えられないかぎり、なにも手に入れられない。市場の論理は、その不公平な配分の責任を過剰に個人に押しつける。(P130〜131)
市場経済に任せておけばすべてOKというのも幻想である。それを是正する役割を国家が果たさなければならないのだ。