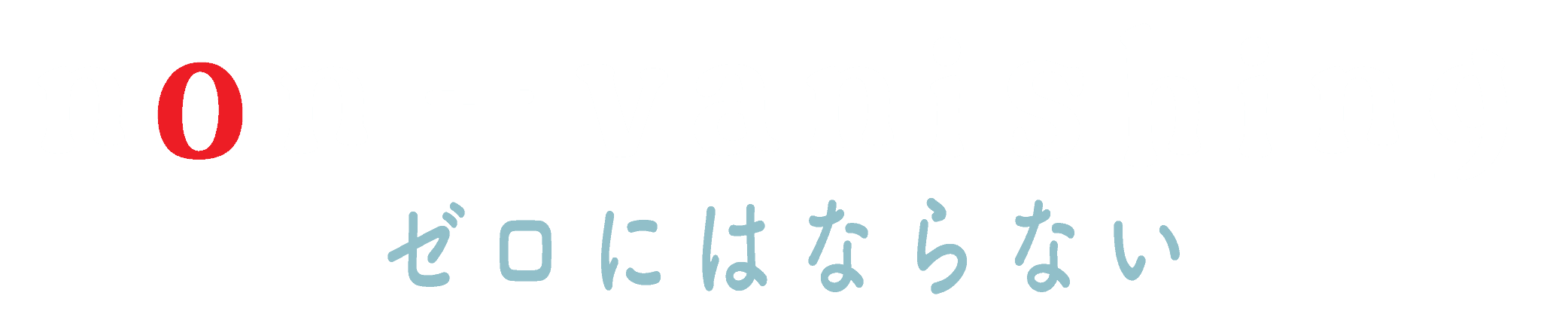実に唐突なんだけど、郵政民営化って結局やって良かったのだろうか、良くなかったんだろうか。
Wikipediaによると「日本郵政グループ発足式」が開催されたのが2007年10月1日だから、今世紀初頭に登場した異色の首相 小泉純一郎の「劇場型政治」によって民営化されてからもう11年も経ったことになる。さすがにこれだけ経てば混乱も収まり、メリットもデメリットも明らかになって、客観的な評価ができるはずだ。と言っても、もちろん僕には知識も能力もないから評価なんてできないんだけれど。
元郵政公社職員も国民だよね。
でも、ふと疑問に思ったことがある。次のようなことだ。
民営化によって郵政公社職員が職を失ったり、非正規職員の増加などによって給与が下がったりしたとしたら、それは国民全体をベースに考えると、デメリットとしてカウントされなければならないのではないか。
ちょっと分かりにくいかもしれない。
郵便のサービスレベルが低下したとか、地方の郵便局が減ったとか、結局料金が上がったじゃないかとか…そういうのは報道で知ることができたり、利用者として実感があったりするんだが、国民からは見えにくいところにもメリット・デメリットがあったはずだよなと思うのだ。
そこで真っ先に頭に浮かんだのが公社職員の待遇だった。
というのも、最近聞こえてくるのは、郵便局で働く人たちの過酷な労働条件や低賃金の話ばかりだからだ。正規職員と非正規職員の格差を減らすために正規の手当を削減するという話もあったし。
見えないところで国民が損失を被っているのでは?
公社で働いていた職員の数は日本有数だったはずだ。その一人ひとりが国民だということを考えたら、もしマイナスに働いた点があったのなら、広い意味で国民が被った損失はバカにできない規模になるのではないかと思った次第だ。(ちょっと屁理屈っぽい)
郵政については国鉄とちがって、債務がどうの赤字がどうのという話はなかったと思う。経営は安泰だったはずで、人件費も事業収益で賄えていた。つまり、民営化しても1円も国庫からの支出の削減にはならなかったのだ。
むしろ郵貯や簡保が抱え込んでいる莫大な資金が問題になっていた記憶がある。たしかアメリカがクレームをつけてきたのではなかったか。
もちろん、眠っていた莫大な資金が有効活用されたのなら、それはメリットとしてカウントしていい。でも、それが何らかの形で国民に還元されたという話は一向に聞かないし、実感もない。
というか、そもそも「良かった、良かった」という話をとんと聞かないのだが。
これってどういうこと?
繰り返しになるけど、郵政民営化は、税負担の軽減という点では国民になんの利益ももたらさなかったが、雇用と所得を(全体からすればほんのわずかとは言え)縮小させたという点で国民生活を圧迫した、たぶん。
でも、この点は「公社時代に比べて人件費をこれだけ抑えることができました」という形でしか表に出てこないだろう。人件費率が下がれば下がるほど「見事なコストカットだ」と賞賛されがちだが、カットされたのは公社職員という国民に他ならなくて、その国民的損失は行政の決算にも日本郵政グループの損益計算書にも損失としては出てこない。
うまく言えないけれど、公務員削減とか公共投資削減などによる行政支出削減を、収支報告だけで考えてはいけないということだ。行政の収支は改善しても、そのツケが他のところで国民に回されることがある。そこまで含めて評価しないと意味がないと言いたいのだ。
まあ、そんなところに考えがいたって、無性に腹が立ってきたというわけだ。ヘンかな。でも、こういうことは他にもたくさんあると思う。一つの収支決算だけを見ていても物事は理解できない。そこに現れない数字があるかもしれないから。
そんなわけで、郵政民営化って、結局どうだったの?