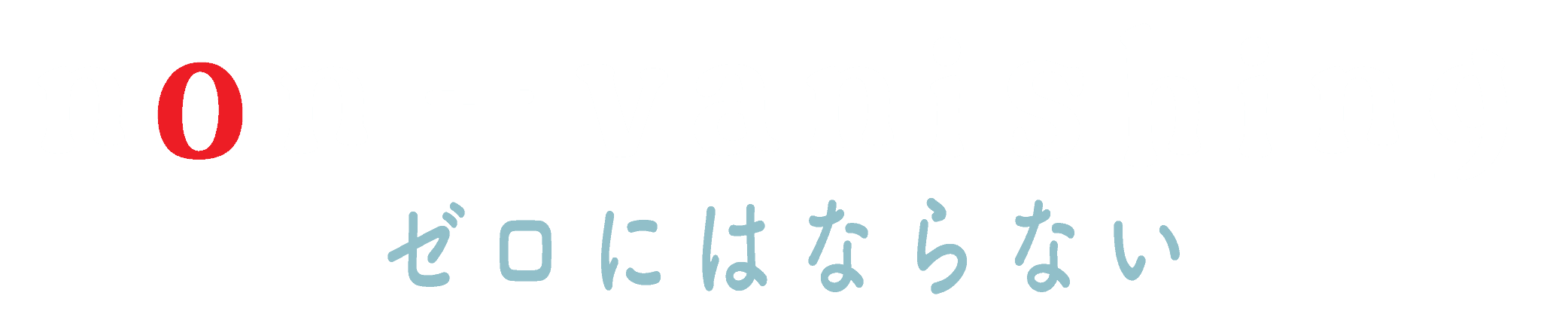戦艦大和の生存者による手記
この本の存在はかなり前から知っていたけれど、読んだのははじめて。

驚くことがたくさんあった。なので備忘録。引用部分はカタカナをひらがなに変えます。
今まで手が伸びなかったのはあの時代や戦争、軍人を賛美する内容だろうと勝手に決めつけていたから。実際に大和に乗り組み、あの劇的な撃沈から奇跡的な生還を果たした将校の手記と聞けば、ついそう思ってしまう。
でも、これもひとつの思考停止。根拠のない先入観だった。
最後の任務は特攻隊の囮になること
無知もいいところなので恥ずかしいんだけど、戦艦大和は特攻隊の囮になるために沖縄に向かったのだとはじめて知った。すでに沖縄上陸をはじめていた米軍に対し特攻隊が体当たりで反撃するにあたり、大和が囮になって米軍の迎撃を吸収するという作戦。
だから燃料も片道分だけで、護衛の航空機もなし。的になるのが目的だから、そりゃ無駄になるものは積む必要はないだろうけど、大和だけで3,000人を超える将兵が乗っていて、しかも他に九隻もの艦艇を率いていたというのに、それがすべて標的の意味しか持たないって・・・?
思っていたよりもずっとマトモで冷静な人たち
幹部がこぞって作戦に反対
でも本当に驚いたのはそんなことではなくて、当時の海軍の、あるいはこの第二艦隊(というらしい)だけのものだったのかもしれないけれど、海軍将校たちの空気のようなもの。これが、いつの間にか抱いていた自分のイメージとかなりかけ離れていた。
まず驚いたのは、この艦隊の司令長官をはじめとする幹部たちがこぞって作戦に強硬に反対したということだった。作戦の内容を普通に考えれば当然のこととはいえ、スゴくないですか?敗戦間際の昭和20年の春に、軍中央が出した作戦に反対するって。そんなことができたんだぁ、と。
これまでさんざん聞かされてきたのは、戦争や軍に対して少しでも批判的なことを口にしたら「非国民」と糾弾されたという話。まあこれは内地でのことだけれど、当然軍隊の中はさらに厳しく統制されていると考えていた。中央が決定した作戦には絶対服従だろうと。
しかもその作戦というのが沖縄に上陸した米軍に対する反撃作戦の一環なわけで、日本にとっては瀬戸際も瀬戸際。イメージ的には刃向かったりしたら即刻軍事裁判にかけられて処刑されてもおかしくないという感じがして。でもこれも私の勝手な思い込みにすぎず、ぜんぜんそんなことなかったわけですね。
軍中央は伊藤司令長官の同期でもある連合艦隊参謀長を派遣して説得に当たらせた。「一億玉砕に先駆けて立派に死んでもらいたい」と。伊藤さんは作戦に対して具体的な問題点を挙げて理路整然と反論したのに、型どおりの精神論しか返ってこない。でも押し切られて作戦遂行へ。
海軍はものが言える組織だった?
ただ、命令が発令されて出航してからも士官の間では喧々諤々議論がつづけられた。しかも「必敗論圧倒的に強し」。そして大方の青年士官は沖縄に着く前に航空魚雷に撃沈されるだろうと予想し、まさにそのとおりになった。「余りに稚拙、無思慮の作戦なるは明らかなり」
日本の海軍って士気が低かったんだと言うこともできるけれど、思ったことを言える組織だったのだという見方もできる。私はどちらかというと後者の印象を受けて驚いた。一直線の上意下達でおしまい!というイメージを勝手に持っていたので。
「一億玉砕に先駆けて立派に死んでもらいたい」と言った軍中央はイメージどおりの愚かさだったのに対し、死地に向かう若者たちが船上で交わす議論は、社会運動に取り組む活動家たちのそれのように鋭く、激しく、忖度のないものだった。
たとえば、米軍飛行士の技術が向上していることや日本の銃器がもはや時代遅れであることを戦闘の生存者が報告しても、中央からは「敵機を撃墜できないのは『訓練の不足による』」と一刀両断されるのが常だったらしい。そういう中央のお偉いさんのコメントが添えられた報告書が回覧されたとき「大馬鹿野郎、●●大尉」と大書署名して回す強者もいたという。
それこそイメージと違う。そして当時の海軍の第一線にこういう人たちがいたということに救いを感じたんだけど、ヘンかな。
軍人を賛美するつもりはないが、自分が勝手に思い込んでいたよりずっとマトモな人たちだったんだと感じたのは確か(軍中央を除く)。そして、ことによると今の日本の一般的な会社より風通しの良い組織だったんじゃないかとさえ思える。将校というエリート集団の中だけの話かもしれないけれど。
米軍の技能向上を素直に賞賛・・・あんな闘い方がしたかったのでは?
実際に自分たちに猛烈な攻撃をしかけてくる米軍戦闘機の操縦技術や戦術は格段にレベルを上げていた。雲に隠れた状態から一気に急降下してきたり、まっすぐ標的に向かうのではなく横移動をして正面にまわり込むなど、こちらの迎撃を巧みに逃れる高度な作戦を成功させていた。
それを彼らは率直に称賛していた。多くの仲間を殺され、自らも死の淵をさまよいながらも、プロの軍人として客観的に相手を評価し、優れたところを讃える。極限状態の中でも思考力を保っている。
「戦闘終了まで体当たりの軽挙に出ずる者一機もなし」
悔しかったんだろうと思う。自分たちがしたかったのはあの米軍のような闘い方だったと感じたのかもしれない。
司令長官の独断で作戦は中止された
もうひとつこの本ではじめて知ったこと。この第二艦隊は玉砕したのではなく、大和沈没が避けられなくなった時点で司令長官の独断で作戦を中止し、生存者救出と帰還が命じられたということ。
著者は言う、「さるにても果断なりし、伊藤長官の作戦収拾命令」。「一億玉砕の合言葉高き折の、しかも乾坤一擲の特攻作戦にして、独断これを中止せしめたるは、並々ならぬ決意を示す」。
スゴいと思うなあ。
伊藤長官の戦場での姿はウソみたいに美しいし、著者を含む青年士官たちの思念や議論は深く、悲しい。戦死した同僚たちの横顔や家族の話にも心にしみるものがたくさんがある。
(2017-09-29)<twitterに投稿>