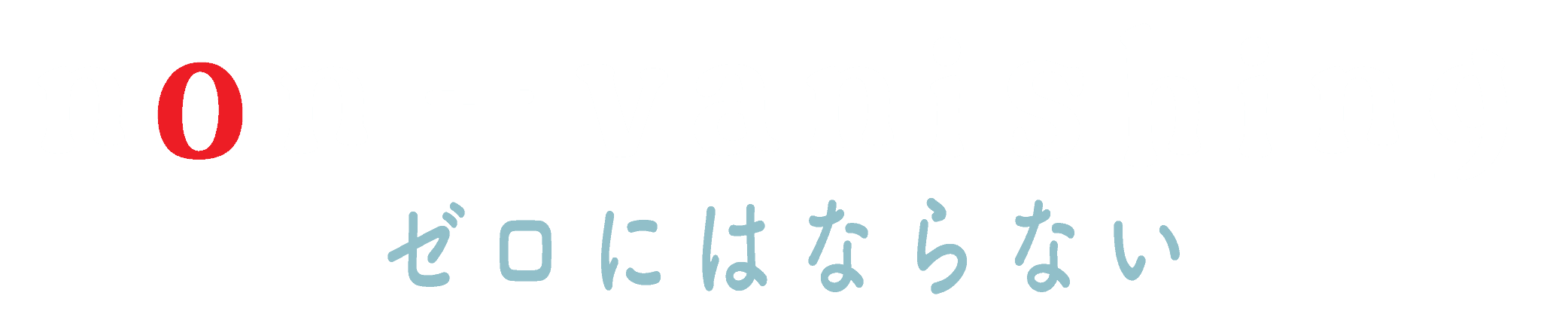目次
「カンニング竹山の土曜The NIGHT」
これから書くことは、カンニング竹山というお笑い芸人のネット番組を見ていて驚いた話なんだけれど、彼を非難したりバカにしたりする意図はまったくないので、それをはじめに断っておく。
去年の11月18日、インターネットテレビAbemaTVの彼の番組「カンニング竹山の土曜The NIGHT」で、「田端信太郎VS藤田孝典公開討論!」という企画が放映された。

「田端信太郎VS藤田孝典公開討論!」
本題に入る前に、この公開討論が企画されるまでの経緯を簡単に説明しておく。まずお二人のプロフィールから。
田端信太郎氏と藤田孝典氏のプロフィール
田端信太郎氏は、ネット通販大手株式会社ZOZOのコミュニケーションデザイン室長。でも、たしか去年の春ぐらいまではSNSプラットフォームLINEの上級執行役員として広告事業のトップにいた人だ。そしてLINEにいた頃から、いわゆる勝ち組として弱肉強食の競争原理を肯定するというか、端的に言うと弱者をいたぶるような攻撃的な発言をtwitterで発信し、頻繁に炎上してきた人でもある。
藤田孝典氏はその対極にいる人と言っていいだろう。NPO法人ほっとプラス代表理事で、貧困問題に取り組む社会活動家だ。まだ若いが著書も多数ある。そして、この人も以前からtwitterで積極的に発言してきた人だ。政府の施策や無策、時事問題などを取り上げ、貧困問題に対する国民の関心を喚起しようと発信を続けてきた。当然その矛先は政権与党だけでなく経営者・大企業・富裕層にも向けられる。彼ら勝ち組の責任にも鋭く言及し、糾弾しているのだ。田端氏とは完全に敵対する立場である。
ZOZO前澤会長の宇宙旅行をめぐるツイッターバトル
昨年の秋、twitter上でこの二人が差しで激しい論戦を戦わせた。ほとんど泥仕合と言ってもいいような猛烈な非難の応酬だった。
きっかけは、ZOZOの前澤友作会長の宇宙飛行の件だった。これも説明しておく。
昨年9月、アメリカのロケット製造会社スペースX社(イーロン・マスクCEO兼CTO)が手がける月周回飛行事業の、最初の宇宙船の全シートを前澤氏が購入したという発表があった。月の周りをターンして帰ってくるだけだが、宇宙飛行士としてではなく乗客として、つまり旅行者としてそれを楽しむらしいから、人類初ということになるのかもしれない。代金は明かされていないが、全9席で750億円以上という試算もある(BUSINESS INSIDER JAPAN2018/9/18)。
彼はその事業に投資もしているらしいから、もしかしたら(事業を前進させるための)追加投資的な意味合いもあるのかもしれないが、それにしても目のくらむような金額である。で、発表直後から賞賛の声も上がった一方で、批判的な意見も少なくなかった。
藤田氏も批判をtwitterに投稿した一人だった。(詳細は覚えていないが)そんなにお金が有り余っているのなら、ZOZOの非正規労働者の給与を上げたらどうかという主旨だったと思う。これに田端氏が噛みついたわけだ。ちゃんと税金も払って社会的責任を果たしているんだから、稼いだ金を何に使おうと勝手だろうと。それに対して藤田氏は、高所得者の税率は低すぎるし抜け道もいろいろある、その一方で非正規労働者が低賃金に喘いでいるのは不公平だと反論した。そこから、前澤氏はこれだけの税金を払っている、とか、社内から待遇に関するクレームは出ていない、いや自分に相談が来ているといったやりとりが衆人環視のもとで延々と続けられたのである。11月18日の生放送の頃もまだやっていたと思うから、1か月以上は続いたことになる。
そして、(これは記憶が確かではないが)前澤会長が田端氏に公開討論会を提案したのではなかったかと思う。もしかしたら二人のtwitter 上の論戦に前澤会長がリツイートで参戦したのだったかもしれない。それをAbemaTVのスタッフが知り、番組で企画した——そういう流れではなかったかと思う。
生放送
番組のことは僕もTwitterで事前に知っていたから、それなりに楽しみにして視聴したのだけれど、結局あまり面白くなくて途中で見るのをやめてしまった。田端氏は予想どおりサディスティックで品がなく、見ていて気持ち悪かったし、藤田氏はTwitterの投稿ほど切れ味がなくて、ちょっと弱々しく感じたからだ。ま、でも藤田氏を責めるつもりもないし、これまでどおり敬意を感じているけれど。
本題 〜「搾取」という言葉はもはや死語?〜
えー、ここからが本題。ここまでは前置きにすぎなくて、言いたいことは、こうした経緯からちょっと外れたところにある。
大人が三人いて、誰も「搾取」という言葉を知らなかった
田端・藤田両氏が登場する前だったと思うが、MCを務めるカンニング竹山氏が、上に書いたような経緯や現在の日本の雇用をめぐる問題、資本主義の基本的な構造などについて、何枚ものパネルを使って説明を始めた。
で、その中に「搾取」という言葉が出てきた。
驚いたのは、竹山氏がこの言葉の読みも意味も知らなかったことだ。聞いたこともないという感じだった。
搾取<さくしゅ>
資本家・地主などが労働者や農民などに労働に見合った賃金を払わず、その利益のほとんどを独占すること。(明鏡国語辞典)
まあ、パネルはスタッフが用意したのだろうし、事前のレクチャーが足りなかったのだろう。……いやいや、そういうことじゃない。竹山氏は1971年生まれだから、このとき47歳。その年まで「搾取」という言葉に一度も出会わなかったのかと思うと、僕にはそれが一つのカルチャーショックだった。
彼だけではない。男女各1名の若いアシスタントが共演していたが、その二人も同様だった。結局、竹山氏は適当に意味を類推して(当たらずといえども遠からずではあったが)そのパネルの説明を終えた。読みは最後まで間違ったままだった。スタッフからのサポートはいっさいなく、その後の訂正もなし。(途中までしか見ていなかったので、その後あったのかもしれないが。)
「搾取」は構造的不公平を示す言葉
もう一度断っておくけれど、「搾取」も知らないのかとバカにしたいのではない。単純に驚いたのだ、成人が三人いて、誰一人「搾取」を知らないということに。ということはつまり、「搾取」はもう死語なのかもしれない、と。そして、「搾取」が死語ならば、「資本家」や「プロレタリアート」もそうなのかもしれない。
でも、藤田氏が主張しているのは、まさに「資本家」による「プロレタリアート」からの「搾取」の話なのだ。前澤会長がそんなに儲かっているのなら、もう少し労働者に還元してもいいのではないかと訴えているのだから。搾取しすぎなのではないかと言っているのだ。
「搾取」という概念は、労働者が働き、その対価を資本家(経営者)が払うという外形的な関係の裏に、圧倒的に資本家に有利な構造が潜んでいることを教えてくれる。だから重要なのだ。弱い立場にある労働者がその構造を知って目を光らせなければ、いくらでもピンハネして対価を削り取られてしまう。労働者の不利益を抑えるために是非とも知っておかなければならない言葉なのだ。
この番組を企画した人間も、「搾取」という概念を踏まえないと議論が成り立たないことを理解していたはずだ。だから、最初の説明に使うパネルにこの言葉を書き込んだのだろう。
なのに、MCが「搾取」という言葉自体をそもそも知らず、どうやらパネルについての擦り合わせもできていなかった。
そして、この重要な前提がうやむやにされたまま公開討論が始まってしまった。
「搾取」が死語になるということは…
「搾取」という言葉が使えなければ、当然この構造的な不公平が視界に入ってこない。資本家(経営者)と労働者は、ヘタをすればただの勝ち組と負け組の関係になってしまう。金持ちと貧乏人。
そして実際、「田端信太郎VS藤田孝典公開討論!」はそういうレベルの話に終始した。田端氏が搾取を知らないとは思えないが、彼が強弁したのは終始、ちゃんと納税しているとか、努力した者が儲かって何が悪いとか、待遇が気に入らなかったら転職したらいいとか——要するに社会について考えの及ばない、お子様レベルの話ばかりだった。公共心とか社会貢献とか、そういうこともまったく頭にないように見えた。
しかし、攻撃的にまくし立てるから、藤田氏は終始守勢に回り、話がかみ合わない。途中で見る気が失せたのは、それにうんざりしてしまったからだ。
「搾取」が死語になった世界では、これが普通のことになるのだろう。誰も資本主義が宿命的に孕んでいる不公平に思いが至らなくなる。勝ち組と負け組、金持ちと貧乏人がいるだけ。勝ち組(金持ち)になれなかった人は能力がないか努力の足りなかった人であり、自業自得ということになる。
資本主義経済においては大多数の労働者が虐げられる構造になっているのに、それを誰も理解できなくなる。
それでいいのか?
言葉は時代とともに移り変わるものだから、新しく生まれる単語もあれば死語となって消えていく単語もある。それは分かる。でも、「搾取」が死語になるって、とんでもないことなのではなかろうか。社会構造の理解の仕方が一つ失われるということだ。「搾取」は、労働者の生活がなぜ苦しいかを一言で言い表してくれる偉大な言葉だ。労働者が待遇改善を求めることの正当性の根拠となり、その結果、労働者の地位向上に大いに貢献してきた。
搾取という考え方が間違っていると証明されたわけでもないのに、消えていくのだろうか。たんにマルクス主義が廃れ、労組の組織率が下がって、資本と労働の関係について人々が語らなくなっただけだろうに。
搾取そのものはこれからも(たぶん永遠に)なくならないのに、言葉だけが消えていくのか。
いいのだろうか、本当に?