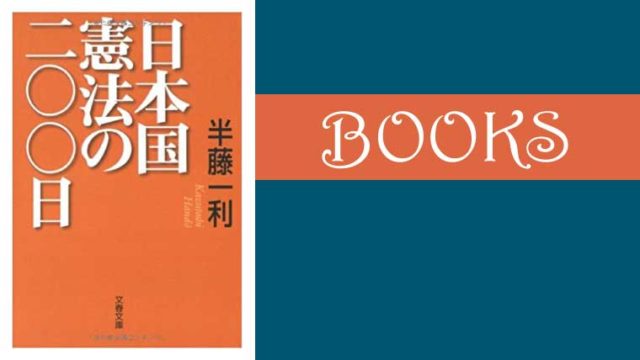2017年レバノン・フランス
監督:ジエド・ドゥエイリ
2017年ベネチア国際映画祭 最優秀男優賞(カメル・エル=バシャ)
2018年米国アカデミー賞外国語映画賞ノミネート
監督はレバノン人。20歳でアメリカに渡って映画を学び、ハリウッドでクエンティン・タランティーノのカメラ・アシスタントをつとめるなどした。
レバノンという国
知れば知るほど絶望的になる…内戦が残したもの
舞台は中東のレバノン。中東と言えば政情不安で…と日本人は思ってしまうが、描かれるのは戦争でもテロでもなくて、我々と変わらない平穏な日常生活を営む市民たちの姿だ。もちろん日本と比べると貧しくて、人々の身なりも貧相だし街も汚い。失業者も多そうだ。でも、軍政が敷かれているわけでもなければ、原理主義的な宗教の影響下にあるわけでもない。例えるなら、日本の昭和30年代がちょうどこんな感じだったかもしれない。
物語の発端は、どこの国でも日々起こっていそうな小さな諍い。それが裁判に発展し、国を二分するような大騒動になっていく。その過程で、この国のそう遠くない過去に起こった不幸な出来事=内戦の詳細と、それが今も人々の心に残す傷痕が明らかになっていく。平穏な暮らしを取り戻しはしたものの、心の傷が消えたわけではなかったのだ。
平凡な中年男二人の喧嘩の背後にある内戦の影。
兵士として戦ったわけではないにしろ、二人は敵同士の立場で内戦を生き延びてきた。ともに身近な人間を殺されたり住まいを奪われる経験をしている。レバノン人なら誰もが知っているような残虐事件を、彼らは当事者として体験していたのである。
内戦終結から四半世紀が経っているが、今も人々の心の中には深い爪痕が残っている。しかし、おそらくレバノン国内でもそれはタブー視されているのだと思う。思い出したくもない暗い過去として。この映画は、誰も触れようとしなくなったその暗い過去をあえて掘り起こし、見つめ直そうとする。
映画で取り上げられたのは内戦のごく一部にすぎないのだろうが、主人公の二人がどんな悲惨な目にあい、どういう人生を歩んできたのかが無知な僕にもよくわかった。そして、わかればわかるほど絶望的に思えてきた。大事な肉親や友人を殺したり、住まいや故郷を奪ったりした敵を許すことなど永遠にできないだろう。無知や偏見から生じた差別とはまったくレベルの違う、実体験に根ざした憎悪なのだから。
レバノン内戦…予備知識として
今は観たばかりだからいいけれど、背景が複雑なので、半年もしたらわけがわからなくなりそう。だから、物語の前提となるもの−−−レバノンという国とそこで起きた内戦−−−について、わかる範囲で少し整理しておきたい。前述のように映画で描かれたのは内戦のごく一部にすぎないだろうし、微妙なニュアンスを感じ取れなかった部分も少なからずあると思う。実際、何を意味するのかよくわからないシーンもあったし。あくまでも僕が理解した範囲の、かなり偏った内容になるとは思うけれど。
レバノン共和国
レバノンは北から東にかけてはシリアと、南はイスラエルと隣接し、西は地中海に面する西アジア・中東の共和制国家。地理的には不幸としか言いようがないくらい危険な位置にある。首都はベイルート。
宗派のバランス
キリスト教徒が最大勢力であるという点がこの国の特徴だが、そうは言っても圧倒的多数を占めるわけではない。国民の40%を占めるにすぎず、イスラム教徒がスンニ派とシーア派に分かれるため相対的に優位にあるだけだ。宗派間の微妙なバランスのうえに成り立っていると言っていい。そして、パレスチナ難民の流入によってそのバランスが崩れてしまう。1970年にヨルダンを追われたPLOがベイルートに拠点を移し、それとともにパレスチナ難民が流入してきたのだ。
内戦
やがてレバノン人のキリスト教徒とパレスチナ難民との間で襲撃と報復がくり返されるようになる。パレスチナ人を攻撃するためにイスラエル軍が侵攻してきたりするのだから、キリスト教徒たちが難民を災いの元と考えても無理はないだろう。イスラエル軍の援助を受けてキリスト教徒が難民キャンプを襲い虐殺するという事件も起こっている。パレスチナ難民にすれば、レバノン人(キリスト教徒)からもイスラエル軍からも迫害を受けるのだからたまったものではない。彼らも報復をくり返す。
ちなみに、(話が複雑になるが)当時イスラエル国防相としてパレスチナ人への軍事作戦を指揮したのが後に首相となるアリエル・シャロンで、この物語でも(登場はしないけれど)重要な役割を果たす。
また、この映画ではよくわからなかったが、シリア軍がレバノン国内に常駐していたらしい。難民やイスラム系の住民はそちらから援助を受けていたのかもしれないし、シリア軍とイスラエル軍の衝突もあったのかもしれない。(これは憶測。)
とにかく殺し、殺される。それが15年もつづき、1975年にはじまった内戦は90年にようやく終結する。
内戦後のレバノン
内戦終結から30年近く経った今も、難民キャンプには40万人のパレスチナ人が居住しているという。キャンプ内は治外法権が与えられているが、あくまでも難民の扱いで、彼らがレバノン人として迎えられたわけではない。レバノン国内で働くことは認められているが、制約も多く、職種によっては不法就労として摘発される。しかし、その一方で、低賃金で雇える労働力として重宝されているという現実もある。いまや構造的に、難民がレバノン経済の底辺を支えているのである。
主人公の一人ヤーセルも不法労働に従事する難民の一人だ。そして、もう一人の主人公トニーは典型的なレバノン人で、右翼的な思想を持つキリスト教徒。
物語 〜悲劇の体験から生まれる憎悪と、人としての敬意〜
他愛もない喧嘩から…でもその背後には
ささいなことでトニーとヤーセルの口喧嘩がはじまり、勢いでヤーセルが汚い言葉を浴びせる。おそらくキリストを貶める言葉だったんだろう。(字幕では「クソ」とかなんとかその程度の訳しか出なかったのでピンと来なかったが。)後日ヤーセルは謝りに行くが、今度はトニーが暴言を吐き、謝るどころか手を出して怪我を負わせてしまう。怒ったトニーは警察に訴え、告訴する。しかし一審は無罪。それを不服とするトニーは上告し、弁護士による本格的な論戦がはじまった。
他愛ないと言えば他愛のない話だ。
だが、トニーは、ヤーセルが最初に吐いた侮辱の言葉がどうしても許せなかったのだろう。暴力をふるったことのほうが罪は重いだろうが、それは自分がさらにひどい言葉を浴びせたことが原因であることは、おそらく彼にもわかっている。だから、傷害罪で投獄させようとか、慰謝料を取ろうと考えていたわけではない。ただ謝らせたかっただけなのだ。
一方でヤーセルは、一度は謝る気になったものの、そこでトニーに浴びせられた言葉はけっして許すことのできないものだった。トニーはこう言ったのだ。「シャロンに抹殺されていればよかった!」と。以後、トニーに暴力をふるったことの非は認めるが、謝罪の言葉を口にしようとはしなくなる。
控訴審がはじまると主役は弁護士に替わっていた。論戦がヒートアップし、それをマスコミが取り上げる。すると、長い間人々の心の奥底に秘められていたレバノン人vs.パレスチナ難民の確執が表面化し、やがて国家レベルの大問題へと発展していく。だが、そうした盛り上がりに反比例するように、トニーとヤーセルの二人は無口になっていく。
裁判の中で次々と明らかにされていったのが、内戦中の悲惨な殺戮事件だった。キリスト教徒が加害者で難民が被害者であったものもあれば、その逆もある。それを、トニーとヤーセルはそれぞれの生い立ちの中で直に体験していた。家族や同朋を失い、自らも危ういところを生き延びて今の彼らがある。トニーから見ればヤーセルは、自分とその家族・同朋を襲撃した犯人の仲間なのだ。そしてヤーセルにとってのトニーも同じだ。
つまり、表面上は大の大人同士のみっともない喧嘩にすぎないものが、実はレバノンという国が抱える悲しい歴史に端を発していたことが明らかになっていくのである。
内戦後、誰も裁かれなかった
それまでレバノンでは、内戦の恨みを口にするのはタブーとされてきた。トニーとヤーセルのような諍いは日常茶飯事のように起こっていただろうが、あくまでも個人の問題として、事を荒立てずに収めてきたのだろうと思う。だからヤーセルも、渋々ながらも最初は菓子折を持って謝りに行った。映画ではトニーが逆上して暴言を吐き、話がこじれてしまうが、普通ならそうなる前に形ばかりの和解をしてケリをつけたのだろう。
タブーとされたのは、おそらく生活の知恵。というか、そうするしかなかったのかもしれない。
1990年に内戦が終結したとき、誰の責任も問われなかったのだそうだ。キリスト教徒もイスラム教徒(難民)も罪を犯した。と同時に、それぞれが被害者となり心の傷を負った。責任の問いようがなかったのだろう。また、誰の責任も問わないことを条件にしない限り、終戦など実現しなかったのだろう。
その結果、人々の心の傷は各人が自分の中で処理するしかなくなってしまった。シャロンはイスラエルの首相へと出世し、難民虐殺を扇動した右派キリスト教徒のリーダーも引き続き一派の指導者の地位にあり、いまや国会議員に収まっているのだ。仮に自分の親を虐殺した犯人が目の前に現れたとしても、罪に問うことはできないということだろう。誰も罰せられないとは、そういうことを意味する。自分たちが受けた被害に関しては泣き寝入りするしかない。代わりに自分たちが犯した罪も闇に葬られる。口をつぐんで、ただ耐えるしかないのだ。
裁判、そして和解
裁判が進行するにつれ、そうやって長い間封じ込まれていた感情が噴出しはじめる。トニーの支援者(キリスト教徒)とヤーセルの支援者(パレスチナ難民)との間の罵倒合戦がはじまり、しばしば弁論が中断される。法廷の外でも一触即発の緊張感が高まってくる。
マスメディアもセンセーショナルに取り上げたため、控訴審判決は国中の注目を集めた。結果はヤーセルの無罪。暴力をふるったのはトニーの暴言によって心を乱されたからで、この場合は正当防衛と認定できるというものだった。
しかし、当の二人は判決の前に和解を終えていた。ヤーセルがトニーの工場を訪れ、さんざんキリスト教徒に対する暴言を吐き、腹を立てたトニーがヤーセルのボディに一撃を加える。トニーが怪我を負ったときと立場が真逆だが、まったく同じようなシーン。そこがこの二人らしいのだが、どちらも最後まで謝罪の言葉は口にしないし、笑顔さえ浮かべない。それでも観ている者には、お互いの謝罪が済み、一件落着となったことが伝わってくるシーンだった。
裁判によってそれぞれの辛い体験が明らかになっていくと、二人はともに相手への同情を禁じえなくなっていく。(無論、口に出したりはしないが。)また、皮肉なことに、弁論を通じて実は二人が似たもの同士であることも浮き彫りになっていった。仕事の種類は違えど、二人の仕事に対する取り組み方は兄弟のようによく似ていたのだ。
こうしたことがわかってくるにつれ、二人の表情が少しずつ変わってくる。この変化の描写が見事だ。喜びでも悲しみでもなく戸惑いのようなもの。それまで相手のことを「難民」とか「キリスト教徒」というレッテルでしか見ていなかったが、一人の人間として見えはじめたことへの驚き。法廷、そして国中の熱気が高まっていくのに反して、二人が同じように口を閉ざし、戸惑いの表情を浮かべるようになるのは、このことの表れだった。
そもそもこの事件は裁判で白黒つけなければならないような問題ではない。大の大人が大人げもなく始めてしまったつまらない喧嘩にすぎないのだ。だから大人げない中年男同士、大人げなく決着をつけるのがふさわしい。ヤーセルの雑言とトニーの一撃。でもその瞬間の二人は、レッテルではなく人間同士としてお互いを見ている。偏屈男同士の不器用な和解の様子がとても愛おしい。
救い…人としての敬意
彼らがそのあと友だちになるというわけではないだろう。もう二度と会うこともないのかもしれない。わだかまりが消え去ったわけではないのだから。だが、判決が言い渡され、裁判所を後にするとき、二人は微笑みをたたえた顔でお互いの姿を追った。一人の人間として相手に敬意を抱いていることを、その顔が物語っていた。
このシーンを見たとき、たしかに希望があることを感じた。希望というか救いというか、とにかくそういう明るい何か。
だから、「判決、ふたつの希望」という邦題は、原題よりも的確にこの映画を言い表した秀逸なタイトルだと思う。“THE INSULT”(侮辱)という飾り気のない原題には、もしかしたら日本人には感じられないニュアンスがあるのかもしれないが、だとしても観終わったあとのこの明るい気分までは言い表せていないのではないか。わからないけど。
トニーもヤーセルも、あのくだらない喧嘩の前には感じたことのない何かを胸に刻みつけていた。それは、彼らの人生において大きな位置を占めてきたやり場のない憎悪とはまったく性質の異なるもので、ぼんやりとではあっても希望を感じさせる何かだったと思う。
内戦というものは、考えてみたら他国との戦争よりも深く人々を傷つけるに違いない。仇同士が隣人としてその後も暮らし続けるのだから、記憶はいつまでも鮮明なまま残り、憎悪はかえって時とともに増幅するかもしれない。これでは永遠に救われない…観ている途中で半ば絶望的になっていた。でもジエド・ドゥエイリ監督はそんな中にも希望の可能性を見出していた。
この映画が訴えているのは、過去を見えないところに押し隠すのではなく、事実として認めることから始めようということだと思う。内戦はなかったことにはできないし、その傷は永遠に癒えない。レバノンの人々はこれまで、敢えて触れないことで傷口を塞ごうとしてきたのだろう。だが、結局のところ痛みはいつまでも残り、相手への憎悪も消えない。この二人の喧嘩はその現われだと言っていいだろう。
思い出したくないと考えるのは人として自然のことではあるが、きちんと記憶しつづけることのほうが新しい一歩につながるかもしれない。たとえ禍々しいものだとしても過去をそっくり受け入れたうえで、今を生きる個人としてお互いが向き合うことの大切さ。トニーとヤーセルという二人の不器用な中年男が見せたあの変化は、このことを示しているのだろうと思う。
個人として向き合えば、相手に対する敬意が生まれるかもしれない。すべてはそこからなのだと、この映画は静かに訴えかけている。
映画としての面白さを十分に発揮しながら、レバノンに生きる人々の心の深いところまで切り込んだ、素晴らしい作品だと思う。
(2018年9月10日KBCシネマにて鑑賞)